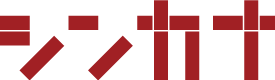今回は JCHO東京新宿メディカルセンター病院の看護部長、野月千春様にインタビューをさせて頂きました。
野月看護部長の手腕と魅力に迫ります。

女性として自立できる職業
看護師を目指されたきっかけを教えていただけますか。
野月:月並みかもしれませんが、小学生の頃に課題図書でナイチンゲールに出会ったことがきっかけです。
また母親から「自立して生きて行きなさい」と教えられており、女性が一人で自立して生きていくには手に職をつけること、
そして、人の役に立つ仕事がしたかったので、看護師以外の選択肢は考えられませんでした。
地元青森の高校に進学しましたが、子供心にできれば東京の看護学校に進学したいと考えており、
所属していた書道部の先生にお話したところ、
「東京厚生年金看護専門学校(現JCHO東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校)には
毎年先輩が進学しているからパンフレットを取り寄せてみれば・・・」、と勧めてくれました。
両親は地元で公務員になってほしいと思っていましたが、
私の熱意と東京厚生年金病院という公的な病院がバックについているのであれば安心だということで、
進学することを認めてくれました。

どのような学生生活でしたか。
野月:寮生活でしたの規則が厳しかったです。
ただしバイトは許可されていて、中華料理店で週に2回ほど働いていました。
大人の定員やお客さんと交わりながら接遇を身につけられ、その後の看護にも役立ったように思います。
例えばお客さんにお水をお出しするタイミングを見計らうなど、
人が望んでいることを予測して動く、人に気を遣うことを学べました。
看護学校に入学した時点では「卒業したら必ず戻る」という話を親としていたのですが、卒業する頃には
「故郷に錦を飾るためにも、看護師として一人前になってからじゃないと戻るわけにはいかない」
と思うようになっていました。
そこで親を説得し当院に就職いたしました。

看護師としてのスタートはいかがでしたか。
野月: 「技術を身につけたい」という希望がありましたので、
将来的に助産師になることも夢に見て産婦人科病棟を希望しました。
産婦人科病棟は明るい病棟でした。
もちろん、流産や障害を持って生まれてくるお子さんもいて、常に笑顔で過ごせた訳ではありません。
しかし、命の素晴らしさをいつも感じられました。
また当時は今よりも患者さんの在院日数が長かったので、
婦人科疾患で亡くなられていく患者さんの終末期に、深く関わることもできました。
患者さんが何を望んでいるのかを考え、私にできることを真剣に探し、一生懸命働いていました。
人間の可能性のようなことを日々感じながら
「こんな仕事に携われて、なんて幸せなんだろう」という思いでいっぱいでした。

業務と看護を切り離さず看護研究として発表
野月:産婦人科病棟に4年弱勤めた後は眼科病棟に異動しました。
眼科には硝子体手術を行う専門医がいましたので、
重症な網膜剥離や糖尿病性網膜症患者さんが全国から集まってきていました。
硝子体手術後、当時はまだ術後2週間、腹臥位で安静を保つ必要がありました。
視力回復を願い、必死で指示された姿勢を守る患者さんを支えたいという気持ちで看護をしていました。
患者さんがその辛い姿勢を維持できるような体位の工夫や床上排泄などは看護技術が求められるところです。
当時のカンファレンスで、排泄(特に排便時)の際の患者さんの恥ずかしさを和らげるため、
オムツをイメージし、便器毎処置用シーツで下腹部・殿部をくるみ、排泄時の音が漏れないようにし、
排泄後は処置用シーツ毎便器を外すことができるので臭気が気にならないよう処理するという方法を開発したりしました。
患者さんから「お通じしたい時頼みやすくなった」と言われた時はとても嬉しく、やりがいを感じました。
患者さんは病院へ病気を治すために入院するのですから、
悪いところ以外の健康な部分の機能を入院前より低下させてはいけません。
そのために看護師は積極的に介入すべきだと思います。

その意味では眼科病棟には工夫すべきことがたくさんありました。
そこで「何が患者さんにとって良いことか」を主題とする看護研究にも取り組み、年1回は学会で発表するようになりました。
例えば、ロービジョン(低視力)の患者さんは病棟内を歩く時に壁際ではなく、廊下の真ん中を歩くのです。
我々からすれば転倒などの事故防止の観点からも壁際の手すりを伝って歩いた方が良いと思い、
手すりを使って歩くよう指導するのですが、そうしません。
理由を尋ねると
「手すりは病室の入り口などで途切れているし、壁際には荷物が置いてあることが多いのでかえって危ない」とのことでした。
そこでロービジョンでも視認できるように廊下の中央の床に赤いラインを引いたのです。
それが非常に好評でした。
合わせてトイレや浴室、病室が区別できるような表示を考案しその成果を看護研究として発表しました。

クリニカルパスの試みとチーム医療の先駆け
野月:また患者さんが治療に参加できるよう、入院中の経過が見えるようなパンフレットを作りました。
今活用しているクリニカルパスの原型のようなものですが、
患者さんにとっては目標を持って入院生活を送る励みもなっていました。
結果的に入院期間の短縮につながったという成果をまとめて報告しました。
もちろん、このような研究には同僚の看護師やドクターに限らず、
さまざまな職種の方と協力しながら進めていました。
チームワークが良かったということでしょうか。
野月:糖尿病患者さんの生活指導は重要であり、眼科病棟には眼科医の他に糖尿病の専門医や栄養士や薬剤師も入っていました。
チーム医療が既に行われていたと言えると思います。

人を育てることの難しさ
眼科病棟での勤務は大変充実されていたのですね。
野月:私は6年9カ月眼科病棟で勤務しましたが、その間専門的な知識・技術を身につけてきましたので、
「眼科看護はこうあるべき」という理想が高くなっていったように思います。
そのために実習に来る学生に高度な要求をしてしまい、
学生指導者である私が厳しいという理由で配属希望者がゼロになるという事態が起きるほどでした。
当時の副看護部長から「1年間、研修学校に行き教育法を勉強してくるように」と指示されました。
「あなたには次があるのだから、そのためのステップだ」と言われましたが
「こんなに臨床で頑張っているのになぜ・・・」と思いましたが、今のままではいけないとうい気持ちもありましたので、1年間国内留学という機会を活かして勉強することにしました。

結果的にはその1年が私のターニンポイントとなりました。
研修学校には素晴らしい教授陣がいて、研修生は皆、切磋琢磨していました。
同期の研修生は看護教員になるという夢をいだき、看護とは何かを常に考える日々で、
同じ志を持つ生涯の仲間を得たのもこの時期です。
本来であれば教員として附属看護専門学校の教員として戻るはずでしたが、
当時の看護部長から学んできたことを活かし臨床で教育委員として力を尽くすよう指示があり、
副師長として現場に復帰し、3年後に師長に就きました。

後編へ続く