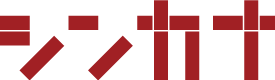今回は神奈川県立がんセンターの大川先生に、がん診療連携拠点病院としての特徴と、先生ご自身の経歴などを伺いました。

工学部を経由して医師を目指す
中:今回は、神奈川県立がんセンター病院長の大川伸一先生にお話を伺います。
先生、どうぞよろしくお願いいたします。
大川:よろしくお願いいたします。

中:まず、貴院の特徴をお聞かせください。
大川:現在、全国の都道府県ごとに、がん診療連携拠点病院が設置されています。
当院は、神奈川県の都道府県がん診療連携拠点病院に指定されており、県内のがん診療の中心的存在です。
つまり、神奈川県内のがん医療を推進する上でさまざまな医療機関と連携しそのまとめ役をする、
より簡潔に申しますと、県内のがん医療を牽引する役割を担っている、がん専門病院です。

中:では続けて先生のご経歴についてお伺いします。先生が医師になられた動機を教えていただけますか。
大川:私は最初から医学部に進んだわけではなく、初めは東京の大学の工学部へ進みました。
大学で工学の勉強とともに社会勉強も積んでいきますと
「自分は人間を相手にする職業が向いているのではないか」という気持ちが芽生え、
二十歳前後には「医学の道へ進みたい」という志が湧いてきました。
結局、工学部を中退し、新たに医学部を受け直しました。
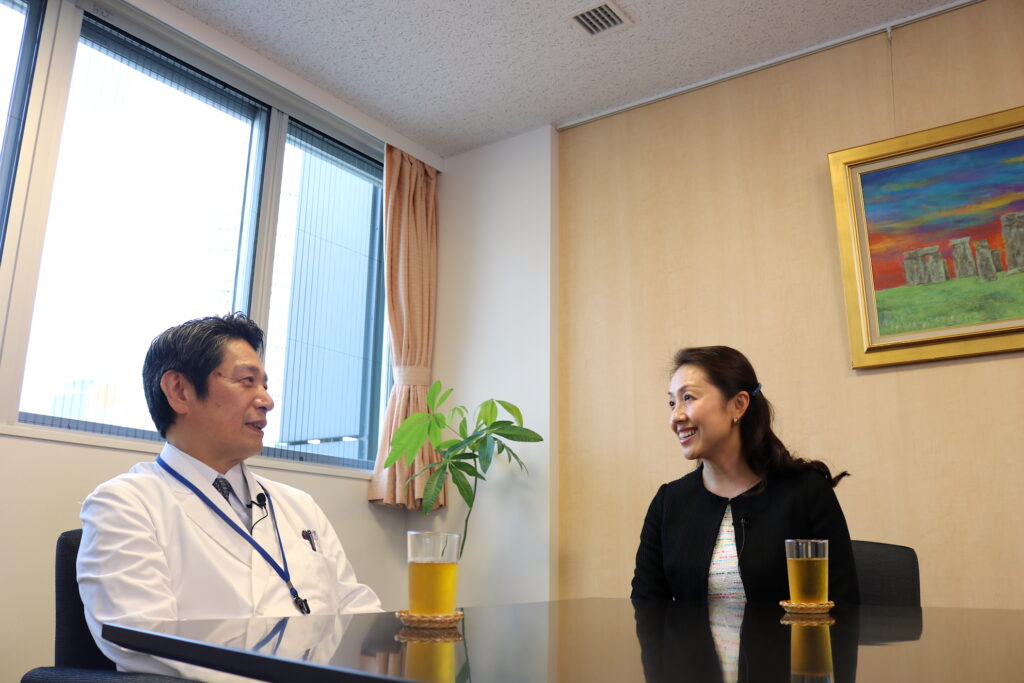
中:少し回り道をされて医師になられたのですね。
大川:私が入学した横浜の大学の医学部は、
クラスの半分ほどがどこかで回り道をしてきた学生で占めていて、少し驚きました。
私もその一人ですが、受験勉強の結果のみで医学部へ進むのではなく、他の領域を経験した上で
本当に医学の道へ進みたい者が医師を目指すという一つのモデルケースにはなったかもしれません。

函館と横浜の生活
中:先生は函館ご出身と伺いました。
東京での生活はいかがでしたか。
大川:高校を卒業するまでの18年間、自分の街の良さを知らずにいました。
函館を離れて時間がたつにつれ、食べ物の美味しさや歴史や観光資源などの魅力に気づき始めました。
東京の印象は非常に活気があり刺激的で、毎日、街の様子が変わっていくように感じていました。
ただ、夏が非常に暑いと感じたのはともかく、冬が非常に寒かったことを覚えています。
北海道の人間は寒さ対策が厳重なので意外に寒がりなのです。
加えて貧乏学生でしたから、防寒具も暖房設備がなかったもので。

中:大学を変わり横浜に移られた時はいかがでしたか。
横浜は歴史も街の雰囲気も函館に似ているのではないかと思いますが。
大川:函館と同じ港町で、幕末から発展したという歴史も重なり、憧れのような感情がありました。
ただ、函館よりもはるかに大都会した。

中:ご出身の函館に横浜が似ていることも、
横浜の大学の医学部に進まれた理由の一つなのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。
大川:確かに、十年、二十年とこちらに住んでいますと
「そういうことだったのかな」と振り返ることが増えました。
ただこれは後付の解釈でして、当時はそこまで詩想に富んではいませんでした。

あえて最も難しい領域へ
中:ご専門領域をお決めになられる時は、どのように決められましたか。
大川:まず、内科向きか外科向きを考えた時「自分の性格では内科系だろう」と思いました。
内科系の主要領域としては循環器内科、消化器内科、呼吸器内科などがあります。
私は内視鏡やカテーテル、あるいは超音波を使う手術をやっていきたいという希望が強く、
それら内科系領域の中から消化器内科へ進むことにしました。
消化器内科と言ってもその幅は広く、大別すると胃や腸などの消化管と、
肝臓や胆のう、膵臓などの実質臓器に分けられます。

当時、胃がんや大腸がんなど消化管の治療は主に外科系が行っていましたが、
肝臓がんはカテーテルによる肝動脈塞栓術を内科医が手がけていました。
そして肝炎や肝臓がんの増加が問題になっている時期でもありました。
このような背景から、肝臓を中心とした肝胆膵領域を専門としていくこと決めました。
自分の医者人生の前半は主に肝臓で、後半は膵臓が専門です。
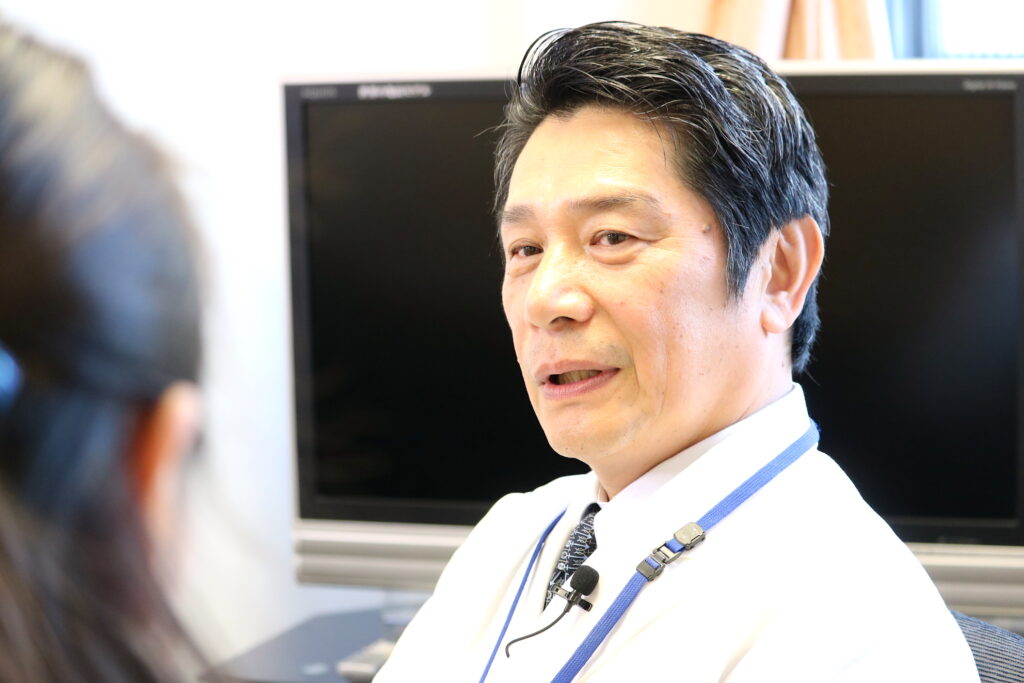
中:膵臓に力点を移されたのはいつごろですか。
大川:初めてエビデンスが示された薬剤であるゲムシタビンが登場した2001年ごろからのことです。
やはり膵臓がんが、あらゆる固形がんの中で一番の難治がんなのです。
しかも増加しつつあることが当時わかっていました。
「一番難しいがんの治療をやりたい」という思いがありましたので、膵臓に力を入れるようになり、今に至ります。
数年前から管理職になり、現在は以前ほど臨床の現場に関わることができませんが、
それまでは肝・胆・膵、そして膵がんを一生懸命にやっていました。

中:あえて難しい領域に挑まれるというチャレンジングな精神は昔からおありだったのですか。
大川:天邪鬼なのでしょう。
先輩からもよく「お前はどうしてそんな厳しいところに行きたがるのか」と言われました。
人間なら誰しも、人から「ありがとうございました」と感謝されると嬉しいもので、
医者の場合は患者さんから「治していただいてありがとうございました」と言われるのが一番の喜びです。
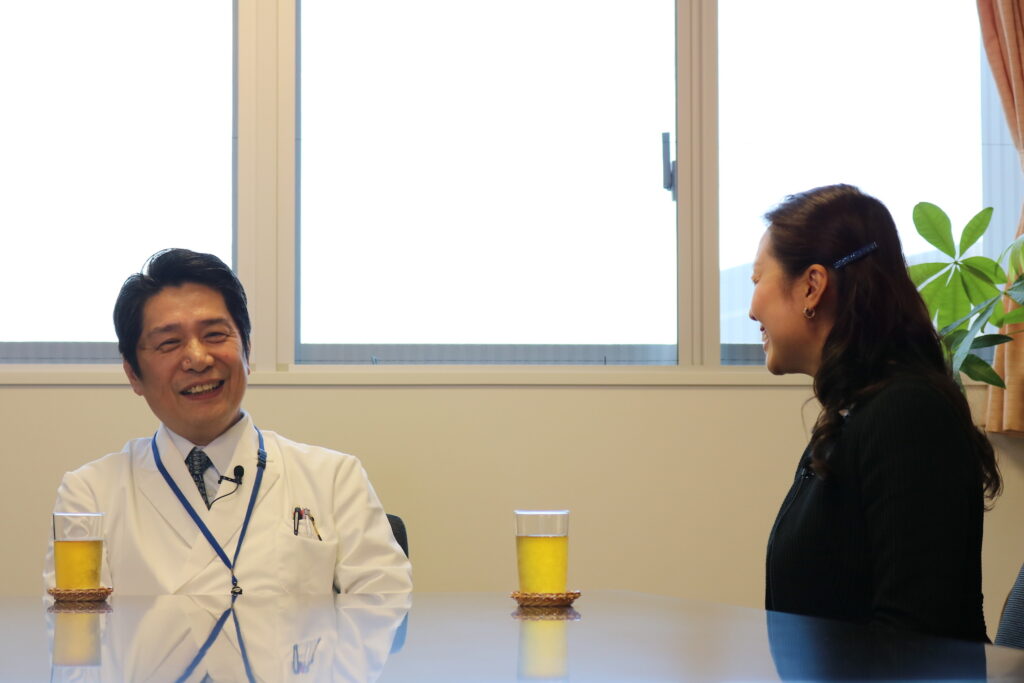
しかし、肝・胆・膵領域のがんは、今後はわかりませんが、当時は残念ながら難しく、
そういった感謝の言葉をいただく機会は希でした。
ただ、誰かがやらなければいけないことは確かですし、治療成績がよくないということは
発展性があるということでもあります。
そういう意味ではやりがいを感じられる領域でした。
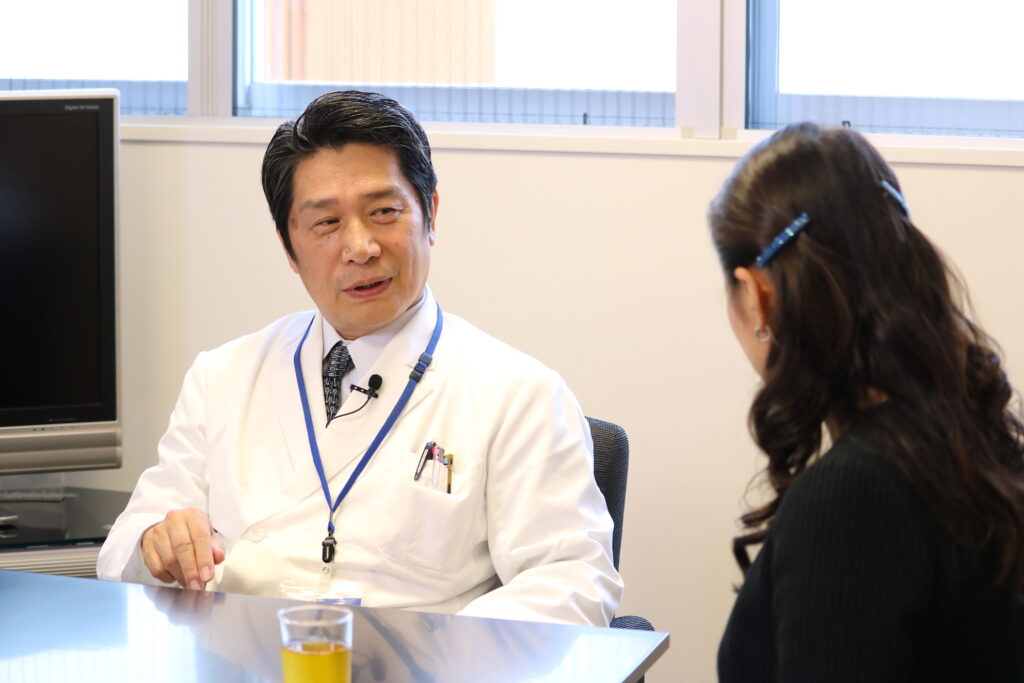
「医者の姿」と「管理職」の姿
中:先ほど、管理職になり臨床に関わることが少なくなったというお話がありましたが、
臨床医から副院長、そして病院長に就任されますと、病院全体をチームとしてまとめ上げるなど、
かなり職務は異なってくるのでしょうか。

大川:まったく違い、今も一応白衣は着ているものの、副院長以降は医者の仕事ではなくなりました。
医者とは、単に疾患の診断と治療をするだけでなく、患者さんとご家族の方の大きな驚きと深い悩みをすべて受け止め、その悩みを軽くしてあげるためにどうすれば良いかとを考える職業です。
例えば、疾患の病勢とは直接関係なく、
患者さんが痛みを訴えた時にも、適切な薬剤を選択するなどして痛みをコントロールします。
言わば、人間と人間の対峙です。
それが医者の姿だと思っているのですが、管理者になりますと
病院の舵取りが第一で、会議への出席や数字相手の仕事が中心になりました。

後編に続く
Interview Team