前編に続きインタビュー後編では、新病院の特徴や、これからの時代に向けた看護師への期待などを
語っていただきました。

リニューアルを機に減床し設備を充実
中:先生は院長として今、どのような病院づくりを目指していらっしゃいますか。
横田:当院には昭和50年代に建設された建物がまだ残っています。
それらの建物が建設された時代は日本全体が成長する中で、どの病院もベッド数を増やして総合病院化し、
先進的な医療に取り組み患者さんを集めようとしていた時代でした。
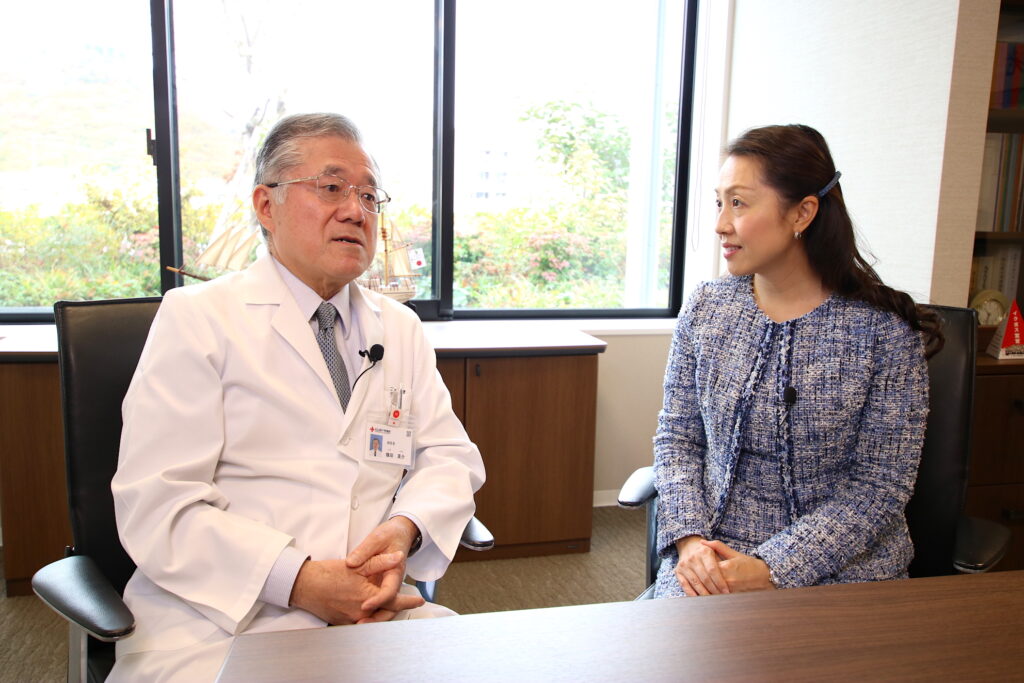
しかし現在は高齢化が進展し、限られた医療資源を効率良く地域で活用すべき時代になりました。
平成9年には総合病院に代わって地域医療支援病院が制度化されました。

その流れの中、当院も当時の院長のリードのもと、今につながるかたちへの転換をスタートさせました。
私はこの流れを引き継ぎ、これからも地域医療を支える役割を果たしていくことを第一に考えています。
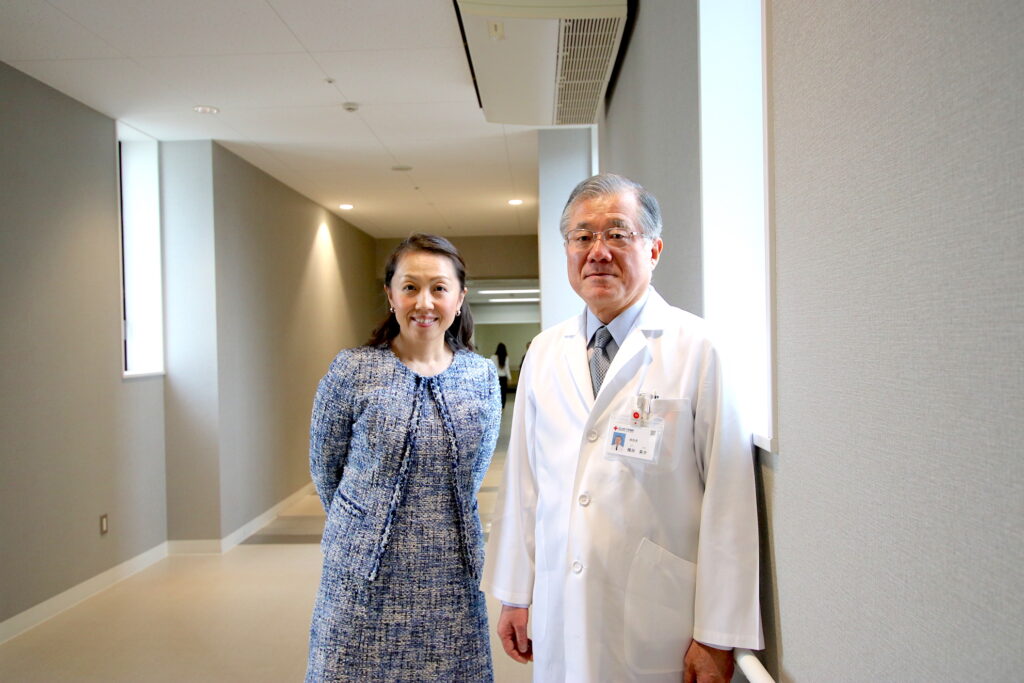
中:病院リニューアルの状況をお聞かせいただけますか。
横田:新病院の建設計画は前院長時代に始まったのですが、
なかなか建設場所を確保できずに遅れていました。
ところが幸いなことに、隣接していた小学校の建て替えで土地が余ることになり、
それを当院が利用させていただくことになりました。
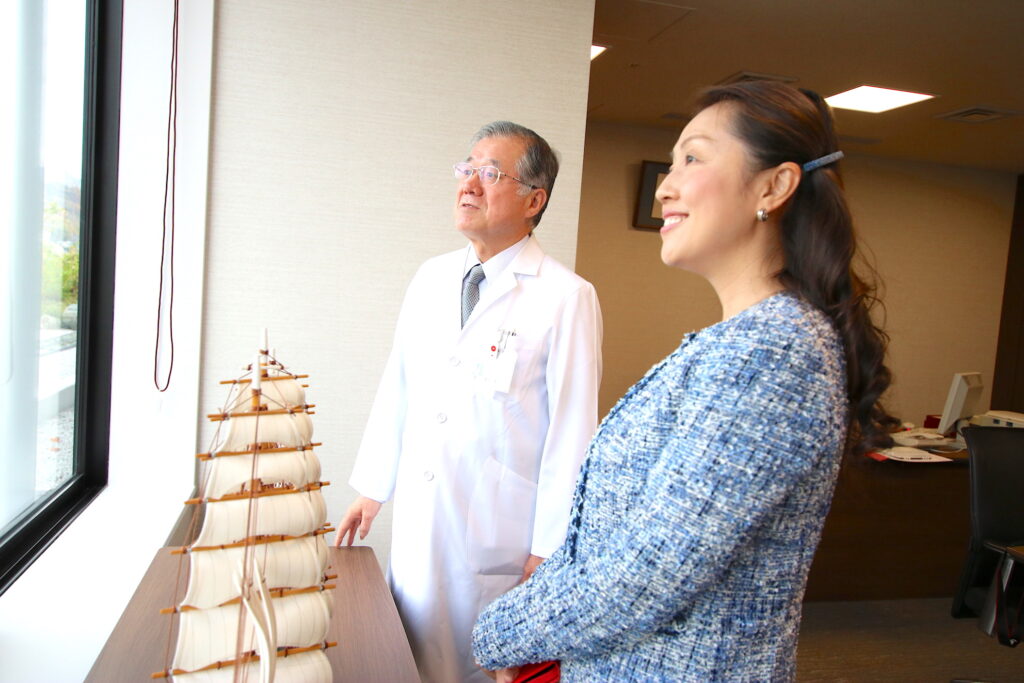
一期工事の北棟が完成し昨年1月にオープンし、現在、二期工事の南棟の建設に取りかかったところです。
当初の計画では前の病院と同程度の680床ほどの設計図でスタートしたのですが、その後、
地域医療構想や地域包括ケアシステムなどの新たな施策が明確になるなどの動きに対応し、
最終的に100床ほど減らし585床としました。

それだけスペース的な余裕が生まれ、職員や学生の研修・実習やアメニティなど
設備面の拡充を図れるようになりました。
建て替えのスケジュールは遅れましたが、
一方で国の医療政策の転換等へ対応した良い病院になりつつあると思っています。
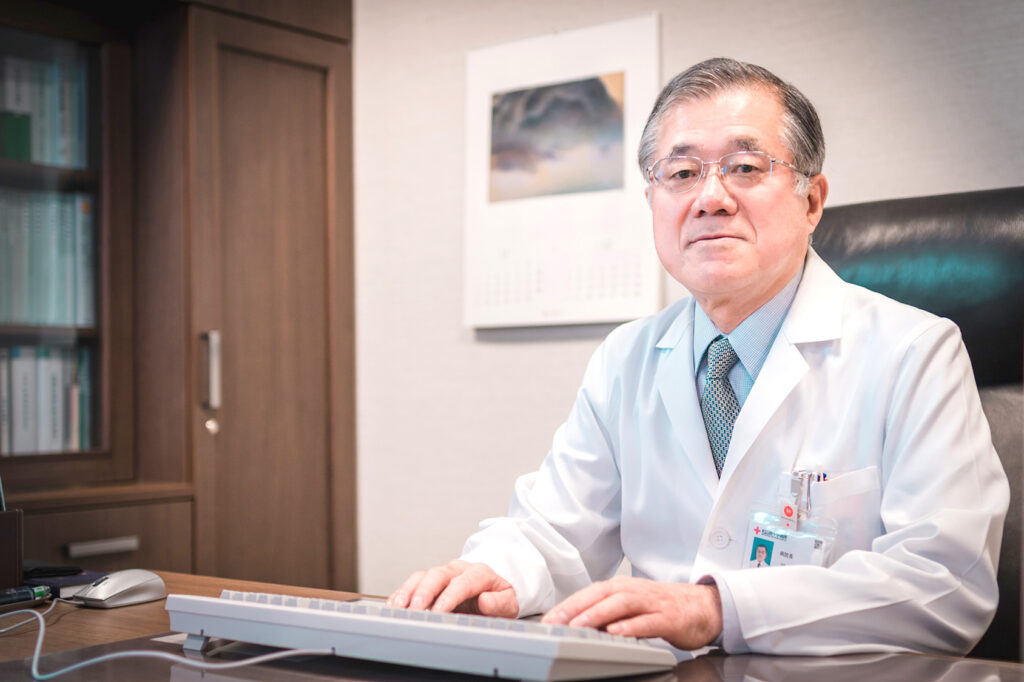
看護師主導の「地域医療連携を考える会」
中:これからも貴院が地域医療支援病院としての役割を果たしていく上で、
先生は看護スタッフをどのように位置付けていらっしゃいますか。

横田:今は医師、看護師や他のコメディカルも含めた多職種で行うチーム医療が求められていますが、
地域医療連携に関しては、やはり看護師の役割が一番大きいと思っています。

一つ具体的な例を挙げますと、連携を始めるに当たって当院の看護師主導で
「地域医療連携を考える会」という会が立ち上げられました。
当初は当院が患者さんを紹介する先の8つの慢性期病院が集まって、
実際に連携を進める現場の担当者が関係を強化したりスキルアップしたりする場として発展してきました。

今では松山医療圏の他の急性期病院から慢性期病院、
さらには在宅医療にかかわる施設等のスタッフまで加わり、
2000年度からは看護師主導で、「病院と在宅看護・介護の連携」合同研修会を毎年、当院で開催しています。

専門性と底辺の広さを兼備した看護に期待
中:先生が求めるこれからの看護師の役割についてお聞かせください。
横田:医学の進歩に従い医療は非常に専門分化してきました。
看護も同様です。
当院にも専門看護師が1名、認定看護師が14名ほどいて、
それぞれの分野で高い専門性を発揮しながら働いています。

もちろんそのような専門性を高めることは大事です。
しかし、これは医師についても同じことが言えるのですが、今後さらに増加する高齢患者さんの多くは
複数の病気を併発しているため、狭い範囲の専門性だけでは対応できず、むしろ底辺を広くして学び、
プライマリーケアの対応力をつけていく必要もあると感じます。

私どもの赤十字病院は全国に92施設あり、いろんな場で情報交換する機会があるのですが、
最近は診療科別の病棟構成にせず、全病棟を全科で共用している病院もあります。
当院も以前は診療科別に病棟が分かれていました。

これを全病棟の混合化は難しいとしても、
ある程度それに近い運用は必要になってくるのではないかと考えています。
そのような中では、看護師は特定の分野に限らず幅広い知識が求められるようになると思います。

新人看護師は1年間、各部署をローテーション
中:看護師を含め、院内のスタッフに向け、先生はどのようなことを伝えたいとお考えですか。
横田:繰り返しになりますが、地域の中核病院として他の医療機関や施設との連携を
大切にしてほしいということです。

加えて赤十字病院は独立採算ですから、しっかり実績を出すことも意識しながら
取り組まなければいけないと思います。
もう一つは、今「働き方改革」と言われるように、職員個々人が自分の生活を大切にして
ワークライフバランスを考え、頑張るところは頑張り、休む時は十分リラックスしてほしいと思います。

中:看護師の働き方に関して、貴院では何か工夫を図られていますか。
横田:当院は、看護専門学校をもち長く看護師の養成を担ってきましたが、今年度末で閉校になります。
そのこともあり今後は新人看護師の育成を目的に、
新たに「研修看護師制度」というプログラムを始めました。

1年目から特定の部署に配属するのではなく、さまざまな部署をローテーションしながら研修を行い
その後、自分の適正を考えて希望を伝え、配属を決めるというかたちをとっています。
このようなユニークな制度を柱に新人看護師の教育・養成に努めています。
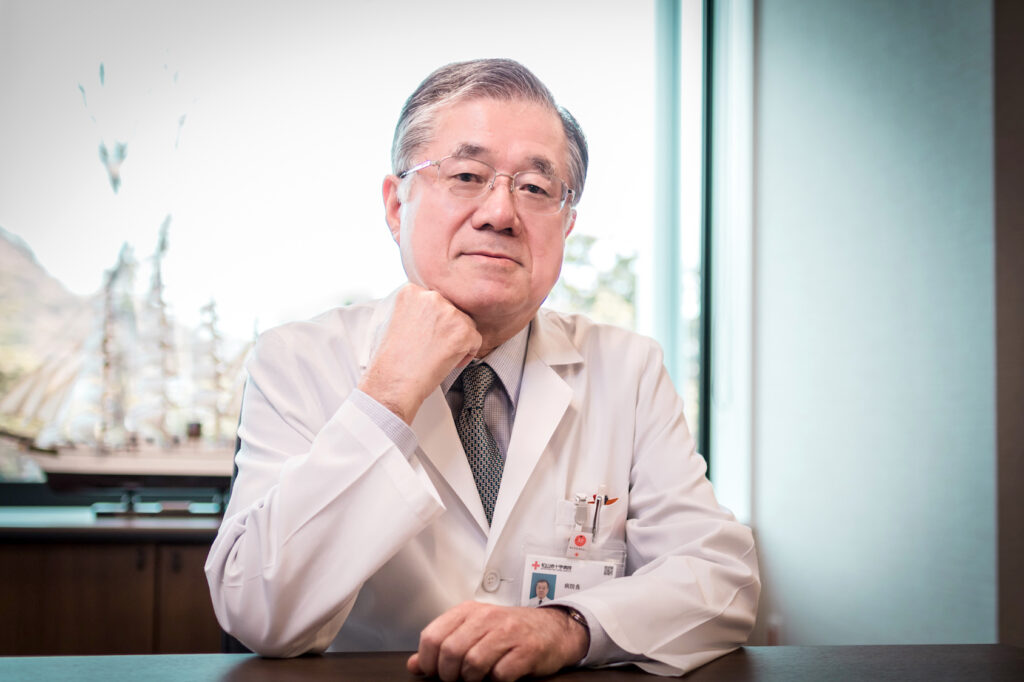
しまなみ海道をウォーキングで踏破
中:最後の質問ですが、先生のご趣味をお聞かせください。
横田:以前はゴルフをしていたのですが、腰を痛めてやめてからはひたすらウォーキングです。
平日は通勤で歩き、土日は特に余計に歩きます。
年に1〜2回は少し足を伸ばして全国各地で開催されるウォーキング大会に参加しています。

この付近では隣の今治と瀬戸内海を隔てた対岸の尾道を結ぶしまなみ海道80kmを歩く
「瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ」というのが10月に開催されており、
私も全体を通して歩いたことがあります。
走るのは苦手ですけど、歩くのはいくらでも歩け、楽しんでいます。

中:ここ松山は、ウォーキングにとても適した町のような印象があります。
横田:そうですね。
道後温泉や松山城、正岡子規に代表される文化の香りにあふれています。
しかも私がこちらに転居して30年になりますが、その間に町全体がたいへんきれいに変わりました。

中:本日は、先生のお優しいお人柄が伝わってくるインタビューにさせていただきました。
ありがとうございました。
横田:ありがとうございました。

インタビュー後記
穏やかな松山という地で、中心となり医療を守る「松山赤十字病院」
横田先生は、医療を、そして地域をとても愛していらっしゃる優しさ溢れる病院長です。
新病院の建設、地域医療連携、高齢化に伴う対策など様々な課題を並行して解決していらっしゃる横田先生。
地元ではない方でも、温かく人を包み込む雰囲気の松山という地であれば、直ぐに馴染むことが出来そうです。
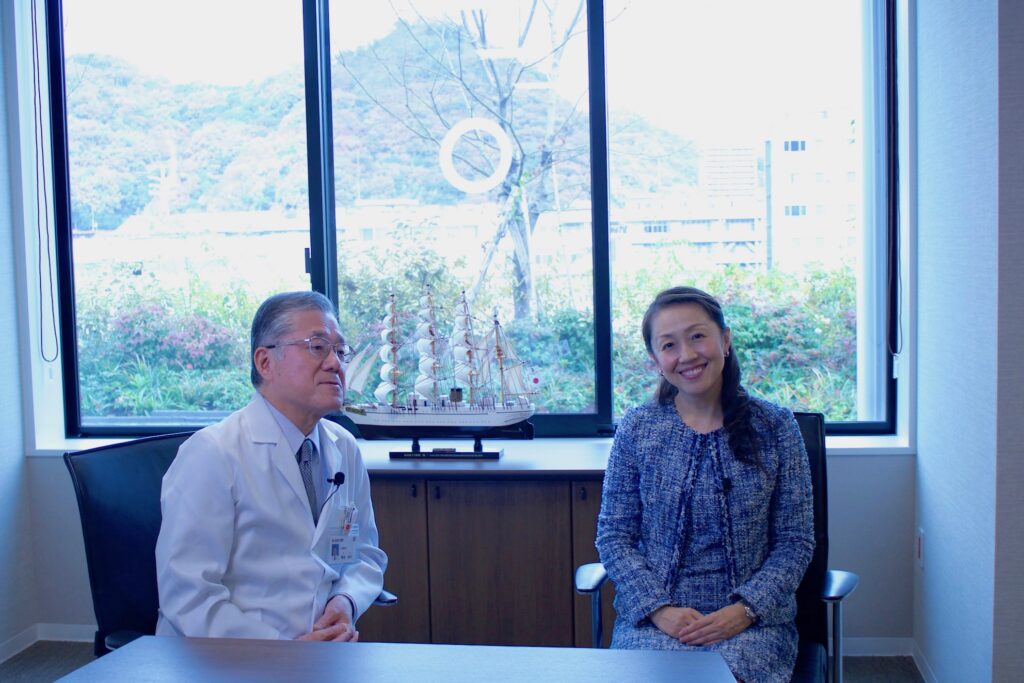
松山赤十字病院関連記事
Interview with Nakada & Carlos




