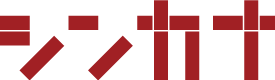今回は新小山市民病院の折笠清美看護部長にインタビューさせて頂きました。
折笠清美看護部長の手腕に迫ります。
養護教諭の土台としての看護師という選択
折笠部長が看護師になろうと思われた動機について教えていただけますでしょうか。
折笠:実は、看護師ではなく、高校の養護教諭になろうと思っていました。
看護学校に3年間通い、その後公衆衛生看護学科に進学して、養護教諭と保健師がとれるコースで1年間勉強しました。
高校の養護教諭は学校にひとりしかいません。
生徒が急変した時に何もできない養護教諭では役に立たないだろうと思い、3年くらいは臨床現場を経験してから養護教諭になろうと考えて、自治医科大学附属病院の看護師として勤務しました。
ですので、こういう看護師になりたいとか、何かをきっかけに看護師を目指したということではありませんでした。
そうでしたか。初めに養護教諭になろうと思われたのは高校生のころですか?
折笠:そうですね、最初は数学の教諭になろうと思っていました。
そこからなぜ高校の養護教諭に変更したのかというと、高校時代は非常に心が不安定ですよね。そんな彼らに対して何か役立てることはないかと思ったことがきっかけでした。
それが今放送大学で勉強している心理学につながっているんです。
だから何十年も課題を引きずっていることになります。
今も学ばれている心理学ですが、放送大学で心理学をメインに専攻されていらっしゃるのですか?
折笠:そうです。
それはもうずっと思いがあって、ということでしょうか。
折笠:そうですね。高校の時もそうですけども、生涯にわたって心理学というものを学んでみたいと思っていて、ずっとその思いは消えずに、今年の4月に入学しました。
養護教諭になるためにもまず、看護学校に入られたかと思うのですが、その時のエピソードはございますか?
折笠:私は生涯で最も勉強したのが看護学校時代でした。
高校まではそんなに勉強するタイプではなかったのですが、看護学校と公衆衛生看護学科での4年間は、とにかくたくさん勉強したと思います。
一番難しかったり、乗り越えるのが大変だった科目はありましたか?
折笠:高校の時は数学が好きでしたので、統計は好きなはずだったのですが、一番苦労しました。
朝から晩まで計算していたような気がします。
今はまったく忘れていますけどね。

養護教諭ではなく看護師として生きることをきめたワケ
学生時代を終えて、いよいよ就職となるわけですが、自治医大への就職は初めから決めていらしたのですか?
折笠:もともと2人兄弟で、兄が進学していましたので、自宅から通える範囲を探していました。
自治医大だったら自宅の小山から通勤できるということが理由ですね。
自宅から通勤圏内で選ばれたのですね。
就職されて初めの1年、不安なこともあったかと思うのですが、思い出やエピソードはございますか?
折笠:自治医科大学附属病院が開院した年に就職したので、スタッフはみんな新しい人たちばかりなので、新人を優しく教育してくれるといった教育制度そのものはありませんでした。
ですから師長さんを頼りにしながら仕事をしていました。
新人で神経内科病棟に勤務していた時、神経因性膀胱炎の男性患者さんがいらしたのですが、この患者さんとの関わりがあったので、結局養護教諭にならずに看護師をずっと続けています。
脳神経を患った方は神経因性膀胱炎を患いやすく、そういう患者さんは、尿意をもよおしてもなかなか出なくて排尿まで時間がかかるのです。
その患者さんは、半身麻痺がある中ようやく起き上がったのですが、そこまでですでに結構時間が経っていました。
私は口に出しては言いませんでしたが、いろんな患者さんがいらっしゃって焦っているわけです、新人ですし。
時間のない中で仕事をしなければなりませんから、「早く終わらせてほしい」という気持ちが自分の中にありました。
きっとそれが表情に出ていたのだろうと思うのですが、その患者さんが察知して「もういいよ」とおっしゃったんです。
その後結婚を機に退職して、子育てをしながら保健師のパートなどしたのですが、そのことがものすごく心に残っていて最終的にまた看護の現場に戻りました。
看護の現場に戻るきっかけとなったのが、この出来事です。
患者さんはお辛いんです。
自分はおしっこをしたくても出ない、こんなに時間を取らせて申し訳ないという気持ちがたくさんおありになるのに、「もういいよ」という言葉を患者さんから発せさせてしまったという私の情けなさというか・・・これは一生涯背負っていく自分の重荷だろうと思って、今から27〜28年前に現場に帰ってきました。

そういった状況では看護の感性が必要になると思うんです。
その時部長は申し訳ないと思われましたが、申し訳ないと気付けない現象も最近では多々あるように思います。
そういった感性はどのようにして形成されたのでしょうか?
折笠:恥ずかしい話、申し訳ないことに気づいたのは数年たってからでした。
「そういうふうに患者さんに言われた、でも何か引っかかっていた」というだけの話で、正直言うと患者さんに申し訳ないと思う気持ちはその時はあまりありませんでした。
数年後、アルバイトで保健師として乳児健診に携わっていたのですが、そこではたくさんのお母さん達と関わります。
子育てを一生懸命なさっているのですけれども、話を聞いていると「子どもが決められた時間にミルクを飲まない」「決められた時間にうんち・おしっこをしないから先生にみていただきたい」という訴えが聞かれて、そういう中で色々気づかされて、「あれ?」と思うことがだんだん大きくなってきました。
いろいろなお母さんたちの話や出来事を聞いていくうちに、「あの時もしかして申し訳ないことをしたんじゃないか」という気持ちになっていきました。
でもそれが、どういう根拠を持って、どういう理論に照らし合わせてそうなったかということが明らかになっていませんでした。
この患者さんに対する何かモヤモヤした思いを払拭するには、現場に帰ってこないとその答えが出せないんじゃないかと思って、27年前、ある病院に就職しました。
そこで私を育ててくれたのが「ナイチンゲール看護理論に沿って看護をしないと、私たち看護師は何のものさしも持っていない」というナイチンゲール看護理論でした。
私の哲学書であり、看護の聖書としてやってきました。
仕事をしていくうちにだんだん気づきが与えられ、「やっぱり私はあの患者さんに申し訳ないことをしていたんだ。
もうその患者さんに直接お返しすることができないけれども、この思いは、今いる患者さんにお返ししていかなければいけない」という思いを持ってずっと仕事をしてきました。
新人ナースがプリセプターの方から「なぜあれがわからなかったの?」と言われた時、「私は気付けないから看護の感性がないんだ」と挫折してしまうようなことがあるという話も耳にします。
ですので、今のお話は新人のナースにとって、希望になると思いました。
折笠:ありがとうございます。私の失敗談です。

信頼があるからこそできた「断らない」というモットー
その後病院に戻られて、管理職としての役割を担うようになったと思いますが、そこでのご自身のモットーはどのようなことでしたか?
折笠:私は当院に去年の3月から赴任したのですが、それまでの25年間、前病院で勤務しておりました。
その時私は、当時の部長から言われたことに対して、異動も含めて、一度も断ったことがなく「はい、わかりました」と応えることが私のモットーでした。
時には6か月で異動したこともあります。たとえ拒んでも、結局は異動することになりますよね。
だから「はい、わかりました」と言った方が、相手は気持ちがいいだろうと考えたのです。
それができたのは、当時の看護部長との強い信頼関係があったからだと思います。
「この方の言うことだったら、きちんと受け入れていこう」という思いがあったのだと思います。
1つは部長との信頼関係であったり、部長の性格や考え方についていこうと思えたこと。
もう1つは、ご自身で意識して断ることをしなかったという、その2つの要素なんですね。
折笠:そうですね。
役割意識もお強いように思ったのですが、例えば「師長をお願いしたい」となった時に、もちろん受け入れはするのですが、戸惑われたことはありませんでしたか?
折笠:あまり戸惑いはありませんでした。
私は最初に循環器の課長を引き受けた時、循環器が大好きなので「よかった」と思ったんですね。
当時、循環器の病棟がうまく機能していなくて、5年のスパンで立て直しを計画していこうと思い「5年やらせて下さい」とお伝えしました。
ところが、1年半たったところで「脳神経外科と小児科の混合病棟が大変なので、そっちへ行ってください」と言われて異動することになりました。
その時に脳神経外科と小児科それぞれの医師のトップがとても快く私を受け入れてくださって、そのことは非常に大きかったですね。
まったく未知の世界でしたけれど「やっていける」と思いました。そこで脳外科の看護を知るにつれ、「ここには看護の原点がある」と気付いたんです。
脳外科の患者さんは、寝たきりであったり、ご自分で意思表示ができない方が多くいらっしゃいます。
そうすると、看護師が手を抜いても誰も文句言いません。
だけど、看護師が一生懸命患者さんのことを思ってケアしたら、素晴らしく清潔になるのです。
ですから、誰かに言われてやるのではなく、自らが看護の楽しさを思い、患者さんのことを考えて看護をしていくという、看護の原点がここにあると思いました。
循環器に心残りがあっての異動でしたが、でも、脳外科でそういう素晴らしい経験ができて楽しかったですね。
脳外科の病棟ですと、他の病棟よりは入院期間が長かったり、また、順調に回復する場合と、麻痺などが残ってしまう場合、さまざまなケースがあると思うのですが、そこでも看護の介入が重要ということですね。
折笠:そうなんです。
看護だけでなくリハビリも、要するに他職種連携ができないと、なかなか患者さんの回復過程を応援していくところには至らないと思うんですね。
でもそれは、病棟に24時間365日いるナースが、きちんと患者さんのことを見て、必要な看護を提供していかなければできないことなんです。
本当に看護の鏡のようなお話です。
折笠:鏡じゃないんですよ、全然。
何かをやるとなった時に、もちろん最初に心残りはあったとしても、行った先の役割を全うしていると、そこの良さがぱっと見えてくることもありますね。
折笠:そうですね。管理職一人でできるものではなく、スタッフみんなと一緒に作り上げていく喜びを感じさせてもらえたのかなと思います。
部署は違っても看護はずっと継続していくという部分で、それを実践されている方のお話は重みが違います。
折笠:ありがとうございます。私は”現場第一主義”なんです。
ですから、前の時病院で看護部長約7年、当院で看護部長1年半、合計約9年近く看護部長をやっていますが、「現場がわからない管理職は管理職でない」ということはずっと言い続けているので、管理職だったらまず現場を知ろう自分の目で見ようということを伝えています。

後編へ続く
新小山市民病院の関連する記事はコチラから
No. 50 折笠清美様 (新小山市民病院) 後編「看護師と看護補助者の協働が拓く看護の未来」