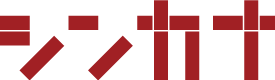脳神経外科医として研鑽を積まれ、現在、療養病棟を中心とする関東病院の院長をお務めの梅川先生に、
お話を伺いました。

ケアミックス型病院として再始動
中:今回は、関東病院病院長の梅川淳一先生にお話を伺います。
先生、どうぞよろしくお願いいたします。
梅川:よろしくお願いします。
中:まず、貴院の特徴を教えてください。
梅川:当院は今から5年前、平成25年の11月に、当地に新築増床移転しました。
元は87床のいわゆる老人病院だったところを、199床のケアミックス型病院として再始動しています。
ご存知のように、数年前から国が地域包括ケアを推進し始めましたが、
当院は恐らくこの地域で最も早く地域包括病棟を開設した病院だと思います。
移転後にも療養病棟を在宅復帰強化型にするなど、この地域の医療体制において、
当院の力を一番発揮できる方法を模索しているという現状です。

中:どのような患者さんが入院されていらっしゃいますか。
梅川:半数以上は急性期病院での治療が終了した後の亜急性期、慢性期の患者さんや、
緩和ケア対象の方です。
他には、例えば整形外科領域のリハビリ目的の患者さんが入院されていますし、
糖尿病のコントロールが悪化し教育入院を受けられる方もいます。
回復期リハビリ病棟ではありませんが、病院としてはその方向を志向しつつあるのが今の姿です。

脳性麻痺だった従姉妹
中:では、続いて先生が医師になろうとされた動機をお聞かせください。
梅川:私には脳性麻痺の従姉妹がいます。
話すことができず自分では何もできない彼女を小さい時から見ていまして
「同じように生まれてきたのに、なぜ従姉妹はこうなのだろう」と、ずっと不思議でした。
小学生ぐらいになり知識がつきますと「きっと脳に原因があるのだろう。
自分が大人になって、このような病気を減らしていきたい」と思うようになり、
自分から親に「中学受験をさせてほしい」と言いました。
そのまま高校を経て医学部を目指したという経緯です。

中:すごい小学生ですね。
梅川:小学生の頃はあくまでも漠然とした望みだったと思います。
ペットをたくさん飼っていた影響で、獣医になりたいと希望が変わった時期もありました。
ただ、基本的には命に関わることをしたいという路線でした。

尊敬する教授の思い出
中:先生は横浜市大で学ばれたと伺いました。
学生時代の思い出に残るエピソードをお聞かせください。
梅川:脳外科の臨床実習の時、クモ膜下出血後の正常圧水頭症の患者さんが入院されていました。
何日も天井を見つめたままで、お話しされません。
手術の前日も同じ容態です。
ところが手術の翌朝いつものように病室に行きますと「おはよう」と声をかけてこられたのです。
「これはすごいな」と思いました。

いま思えば脳脊髄液を腹腔へ流すシャント手術を施行したのでしょうが、
当時はまだそんな知識はありません。
患者さんの劇的な改善に驚くとともに、脳の重要性と脳外科の素晴らしさを体感したエピソードです。

もう一つは、たいへん尊敬していた教授のことです。
入院中の患者さんが、看護師が置いてあった赤マジックを口紅のように塗ってしまったのです。
朝、私が病室を訪れた時に大騒ぎして綺麗に落としたのですが、
その日の回診の時、教授がその患者さんに「○○さん、さっきはお化粧してたね」と言ったのです。
私はてっきり自分たちが最初に見つけて対処し終えたと思っていたのですが、
教授は我々よりも先に病棟をひと回りして知っていたのです。

恐らく早朝6時ぐらいではないでしょうか。
そうとわかった時点で「これは敵わない」と思いました。
医者というものは、そのような責任感を持って患者さんに当たらなければいけない。
教授といえども、そこまで努力している。
その姿は、その後の私のスタンスの大きな方向性を決めました。

脳卒中後遺症へのチャレンジ
中:小学生の頃にお気づきになられた脳の大切さを医学生になり再確認され、
尊敬する教授との出会いもあって、脳外科医の道が信念になったのですね。
ご卒業後にも何かエピソードがあれば教えてください。

梅川:最初の10年は「手術がうまくなりたい」と無我夢中でした。
たぶん外科に進んだ医師は誰もがそうだと思います。
ところが10年くらいたった時、ふと思ったのです。
どんなに手術がうまくいっても患者さんに後遺症が残ってしまう、
脳のダメージはファーストアタックでほぼ決まってしまう。

外科医は「手術がうまくいった」と満足していて、
患者さんがしびれや痛みといった症状に困っていることを、あまり気に留めないのです。
この問題を何とかできないかと思い、インドの伝統医学アーユルヴェーダを習い、
その施術の一つリフレクソロジー(足のマッサージ)を患者さんに施行してみました。
すると確かに習った通りの位置に足のシコリがあり、そこを揉むと症状が改善するようなのです。

他にもアロマセラピーなども習いアドバイザー資格も取得しました。
しかしこれらは保険が通らず、病院にとって一銭の得にならないばかりか、外来の混雑が増すばかりです。
そこで今ではテクニックを看護師に伝え、足浴の時に活用してもらっています。

中:心に残るエピソードがたくさんおありで、
常に患者さんをどのように癒すかという点にフォーカスされていらっしゃると感じました。
梅川:痛いとか辛いのは、私自身も嫌ですから。
急性期病院では患者さんに後遺症があっても次の病院へ送らなければなりません。
ですから急性期の医師は、患者さんのその後の生活をよく知りません。

20年、30年、ずっと辛い症状を抱えたまま生きることは、患者さんにとって大きな重荷です。
外科医時代に感じ始めていたこの思いは、当院に赴任して確信に変わりました。
自分は実情をあまり見ていなかったのだと。

患者と家族の視点
中:そういう意味では、先生は外科医でありながら、
脳神経内科的なアプローチも重要視されているということでしょうか。
梅川:そういうことだと思います。
神経内科を標榜している病院が少ないという問題もあります。
ですから高齢化で増加しているアルツハイマー型認知症やパーキンソン病、てんかんなども
「自分は外科専門だから診ないよ」と言っていられる場合ではなく、勉強が必要です。

中:いま一番必要性を感じていらっしゃることはどのようなことでしょうか。
梅川:やはり認知症の根治薬ですね。
人格の根幹が破壊されたわけではないのに問題が起こりますと、ご家族や周囲の人の負担が増え、
ご本人も辛い思いをされます。
家族会を開きますと「昔はこんな人ではなかった」と涙される方が必ずいらっしゃいます。
そんな時、外来診察では、差し障りのない笑い話をして多少は気持ちをほぐしていただけている
と思うのですが、医者としては無力感で悲しくなります。

後編に続く
Interview Team