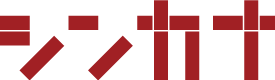院長インタビューシリーズ、今回は国立療養所多磨全生園「園長」である石井則久先生のお話を伺います。
思いを現実に
国立療養所多摩磨全生園の特徴や特色を教えてください。
石井:この療養所は過去にハンセン病を罹った方たちが入所する施設となっています。
170人ほどの入所者に対し350人ほどの職員が勤務しています。
同様の施設が青森から宮古島まで全国で13施設存在します。
全て国立で以前は収容施設という形でしたが、法律が変わり、退所は本人が希望すればできるようになりました。
家族と別れている、あるいは高齢である、または後遺症が高度で社会で生活をすることが難しい方は施設に残ることができます。

医師になられた動機について教えてください。
石井: 地方の無医村のような所で仕事がしたいと考えておりました。
医師は仕事をする場所に制限が必要ない、自由に自らが勤務場所を選択出来るライセンスというイメージを持っていました。
医学部に入学した当初は、無医村の診療補助や家庭訪問をする「無医村のクラブ」に所属していました。
無医村に行き、様々な人と会い、酒を飲み交わすなど、出逢いや繋がりを大事にしました。
また夏に無医村である福島県の都路村(みやこじむら)に行き、家庭訪問後に地域の青年団と飲み交わしました。
都路村の青年は非常に親切な方で、共に生活することが楽しみでした。

ハンセン病との出会い
皮膚科を専門と決めた動機を教えてください。
石井:医学部5年生の時に皮膚科の講義で、ハンセン病の特別講義がありました。
そこで、ハンセン病に特別な意味を感じ、興味を持ちました。
熊本の療養所に行き、神谷美恵子さんの本を見つけまして、ハンセン病が過酷な病気だと知り、ハンセン病に関わるため、皮膚科に進むことを決めました。
皮膚科では臨床と研究に没頭し、免疫病の研究や、基礎研究を20年ほど行ないました。
その間、免疫の研究でドイツへ留学し、皮膚科のスペシャリストになるために努力しました。

皮膚科の楽しさや、研究で喜びを感じる点についてお聞かせください。
石井:一番は、一目見て診断ができる点です。
視診で診断が困難な場合は、患部の皮膚を一部生検、病理検査することでかなりの診断が可能になります。
また、その一部始終を1人で実施できることに対して非常に面白いと感じました。
そして、その知識を患者さんに対して還元することで、治療の幅も拡がります。
仕事をしていくうちに、仕事の幅の拡がりや、海外で研究を行うことへの期待、良い論文を書くことなど、その時々でモチベーションが上がっていました。
ドイツで信頼される

ドイツ留学時代の思い出に残るエピソードを教えてください。
石井: 医師として勤務した3年目に、留学の募集がありました。
自ら立候補し、教授に推薦していただくことが出来ました。
1981年から1983年の2年ほど、ドイツにおりましたが、朝から晩まで研究室で研究をし、夜はギリシャやユーゴスラビア、ポーランド、アメリカなどの若い仲間と飲み交わしました。
当時は、免疫学が非常に盛んな頃で、若い仲間は皆、免疫の研究を非常に楽しんで取り組んでいました。ディスカッションも頻繁に行ないました。
世界中の知恵と知識が集まるこの場所では、研究の志が同じ方向に向いていると実感することができました。
研究だけでなくプライベートでも全員の意志が統一することが楽しかったですね。
ドイツの研究所において、日本人は真面目で有言実行だと、非常に信頼していただき、評価されました。
私が初の日本人留学生として先例を付けたことで、その後も横浜市大の医師が12名ほどドイツ留学し、後輩の道を開いたと嬉しく思っています。

ハンセン病と向き合う時
日本に戻られてからのことをお聞かせください。
石井:大学に戻り、2年間ほど横浜市内にある港湾病院という市立病院で勤務し、また大学に戻るというスタイルで臨床も研究も行ないました。
50歳近くなり、原点であるハンセン病の研究に特化しようと思い立ち、2000年に国立感染症研究所のハンセン病研究センターに入職しました。
研究センターにいた18年間で、ハンセン病の診断や治療のアドバイス、ハンセン病についての相談などハンセン病なら全て受け入れるスタイルにしました。
ハンセン病の正確な知識を持つ人は殆どいません。そのため、患者さんのために啓発運動、或いは教育なども取り組みました。

教育に関しての取り組みについてお聞かせください。
石井:毎年夏に夏期大学という学生向けの講座があります。
また、皮膚科の医者をターゲットにした講習会を実施しています。
こうした活動により医療関係者、或いは医学部の学生、或いは看護学生に対してハンセン病について啓発を実施しています。
まずは医療職がきちんと理解することが大切だと考えております。
一般の方にも啓発を行なっておりますが、特に年配の方は先入観があることは事実です。
理解を得るのは難しい面もございますが、小学生から大学生の若い世代に対しても啓発を行い「昔、偏見や差別受けた病気ですが、正しい知識を学べば、この病気を理解することできる」と教えています。
また、この隣のハンセン病資料館で啓発を行なっており、私も手伝っています。

啓発は理解から始まる
ハンセン病の理解を広める上で、意識されたことは何でしょう。
石井:戦争経験者の言葉と同様に、ハンセン病の元患者が直接、一般市民、一般学生、医学部生、或いは看護学生にその体験を語っていただくことが大切です。
私が話すよりも非常に強いインパクトになります。
自分が悲惨な目に遭ったことを伝えていただくことで、医学部生、看護学生たちも非常に感動しますし、それが一番重要だと思います。
特にハンセン病は、顔に症状が出ます。
治療薬がない時代は、顔の変形、手足の萎縮により仕事や、食事が困難でしたので、社会から排除されてしまいました。
偶然その人が罹患し、後遺症があるだけで、その人が悪いということではありません。
特に医療を目指す医学部や看護学部の学生たちは、しっかりと学んでいただきたいと感じています。
私自身、初めにハンセン病が奥深いと感じられたきっかけも、そこにあったように思います。
特に神谷美恵子さんの「極限の人」などの本を読むと
「なんで私じゃなくてあなたが病気になったのか…?」
と、単純な疑問を投げかけてくれる病気ですし、誰でも病気になるのだと痛感しました。
後編へ続く
Interview Team