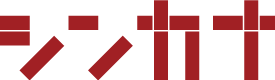今回は下北沢病院の菊池先生に、形成外科を専門とされた経緯や病院経営に関わられるようになった経緯などお伺いさせて頂きました。

形成外科の可能性を感じて
中:本日は、下北沢病院院長の菊池守先生にお話を伺いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
菊池:よろしくお願いします。
中:まず、菊池先生が形成外科を専門とされた経緯をお聞かせください。
菊池:私が子供の頃、男の子の間でロボットが流行っており、
私もよく科学雑誌を読んでいました。
例えば人間とロボットを対比させ、人が手で卵を潰すことなく摘まみ上げるには、
非常に緻密な計算を瞬時に処理していると雑誌に書いてあり、
子ども心に「人間ってすごい」と思った記憶があります。

長じて医学部に進学しますと、
我々の頃はまだ卒業の時点で診療科を選ぶ時代でしたので、
6年生になるといろいろな診療科へヒアリングに行きます。
子ども頃のロボットへの興味の名残か、
その頃もまだ運動器や体表面などに興味があったのです。
そこで進路の候補として、整形外科や形成外科が挙がってきました。

形成外科のベテランドクターに相談すると
「この科には手術がたくさんあって、自分もまだやったことがない手術がある。
しかも医師の数が少ないからいくらでもやることがある。それはもう日々面白い分野だ」
と言われ「ああ、そうなのですね」と形成外科に入りました。
入ってみると、いくら手術をしてもいくらでも覚えることがあり、
いつまでたっても一人前になれません。
これは大変だなと思いました。

中:実際に形成外科医になられて、面白い、
または難しいとお感じになられることはどのようなことでしょうか。
菊池:形成外科は生命の維持のために必要な医学ではありません。
しかし、人が社会生活を営むために求められる整容的な部分は形成外科が担います。
例えば、消化器外科医が癌を摘出した後に患者さんから言われるような
「命を助けてくれてありがとうございます」という言葉を形成外科医が聞くことはありません。

しかし、患者さんが社会生活を送るためには大変必要とされる診療科です。
もう一つの特徴は、患者さんにも結果が見えるということです。
我々が「きれいになった」と思っても、
患者さんがそう思わなければそれは失敗なので、ゴールをどのように見極めて、
どのようにゴールに近づけるかが形成外科の難しいところで、やりがいでもあります。
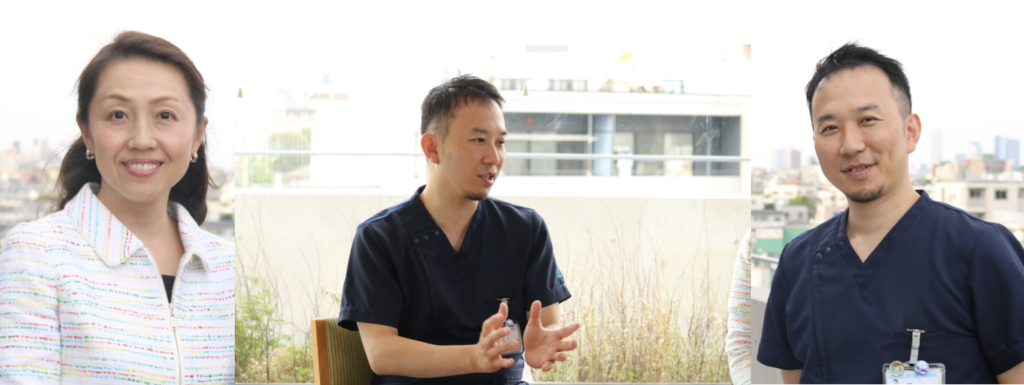
デバイス革新でブレークスルー
中:確かにいま伺っていて気付いたのですが、患者さんは例えば内臓疾患であれば
「終わりましたよ」と言われたとき「ああ無事でよかった」となりますが、
表面的なものですと、ずっとそこに目が行ったり手で触れたりされるかと思います。
形成外科は、患者さんの生活をより豊かにするものでもあり、
一方では逆の結果になる可能性もあるのですね。
菊池:手術によって、逆に患者さんの満足度が下がることもあるので、
手術適応の判断はなかなか難しいところがあります。
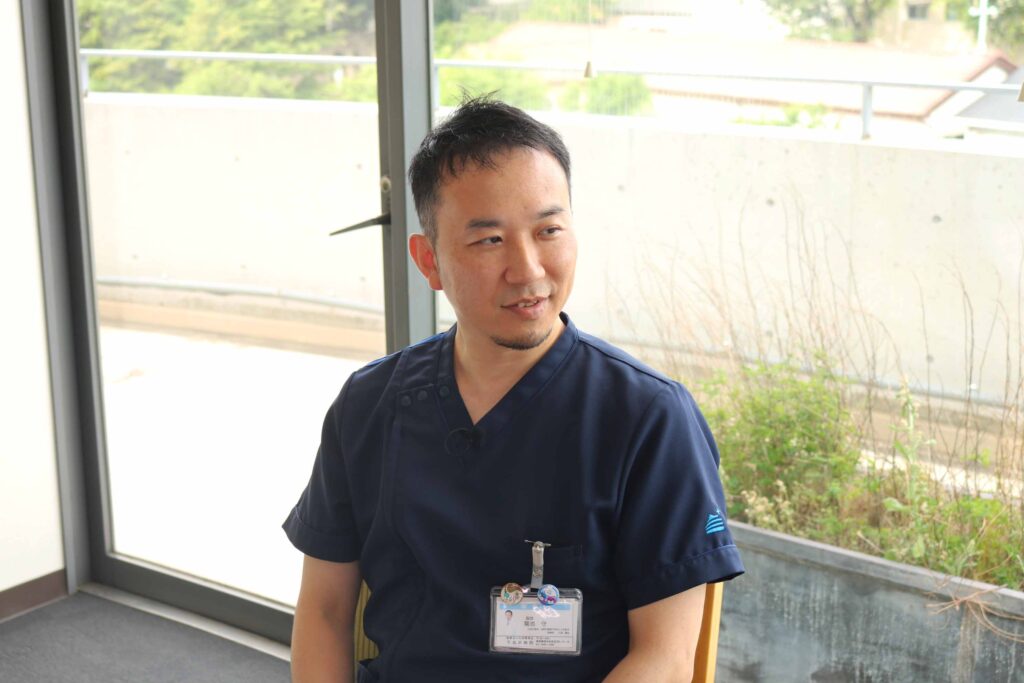
中:先生が学生時代に学ばれた頃から現在までに、
形成外科領域もかなり進歩している部分があるかと思いますが、
これまでの進化とこれからどのように進むのか、方向性をお聞かせください。
菊池:技術的な部分のブレークスルーはやはりデバイスです。
顕微鏡技術の進歩によって、昔はできなかった細かい手術ができるようになり、
昔はつなげなかった血管をつなげられるようになりました。
また創傷治療にも、昔は軟膏を塗るしか手がなかったものが、
今は陰圧閉鎖療法などデバイスが非常に進化しました。

もう一点、手術において、かつては術者の腕に頼るウエイトが大きかったものが、
急テンポで一般化が進んでいることも挙げられます。
以前は上手な医師しかできなかった手術が、今お話ししたデバイスの進化もあり、
誰もができるようになってきたことは、大きな変化です。
さらに進歩すると、これから領域によっては手術の機会が減っていくかもしれません。

医師の腕頼りでない手術を
中:先生ご自身は、やはり子どもの頃から細かい作業がお得意だったのでしょうか。
菊池:自分の手先がことさらに器用だとは思っていません。
ただ、手術の成功は術者の手先の器用さだけでなく、
適切な術前計画やリスクを回避する手術プランニングが重要になります。

そのため現在の手術は、一匹狼の名手を育てるのもさることながら、
いかに技術を一般化・標準化し、システムとしての医療にまで高めるように
シフトしてきているのではないでしょうか。
私は外科医としてスムーズに診療をするために、外来、病棟、手術室、
それぞれの現場でシステムを構築する必要性を感じた経験が何度かありました。
それが今の院長という立場につながっているのかもしれません。

中:ちょうど今お話しいただきましたので、
臨床医から病院経営に関わられるようになられた経緯を教えていただけますか。
菊池:それは足の診療に特化している当院の成り立ちにも関係してきます。
2000年代に入るとフットケアや下肢救済という領域が徐々に盛り上がりを
みせてきていましたが、それに特化した病院はこれまで無かったのです。
その理由は、足病変は一つの診療科では診ることができず、
multidisciplinary approach、いわゆる多職種の連携が欠かせないこと、
かといって大学病院などの大病院では小回りがきかず対応が難しいことなどです。

そこで「足に関しては、ここに来ればなんでも診られる病院を作ろう」
というコンセプトで、形成外科医、整形外科医、血管外科医、
糖尿病内科医、皮膚科医が集められました。
「では誰が院長に」という話になった時、私自身が大学病院の勤務歴が長く、
ある意味ミドルマネジメントをしていたので、私が院長になりました。

後編に続く
Interview Team