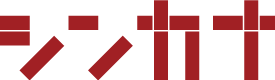グリコヘモグロビンやグリケーションなど糖尿病領域の研究で大きな成果をあげられた
練馬光が丘病院の川上正舒先生へのインタビュー。
その前編では先生のご経歴を中心にお聞かせいただきました。
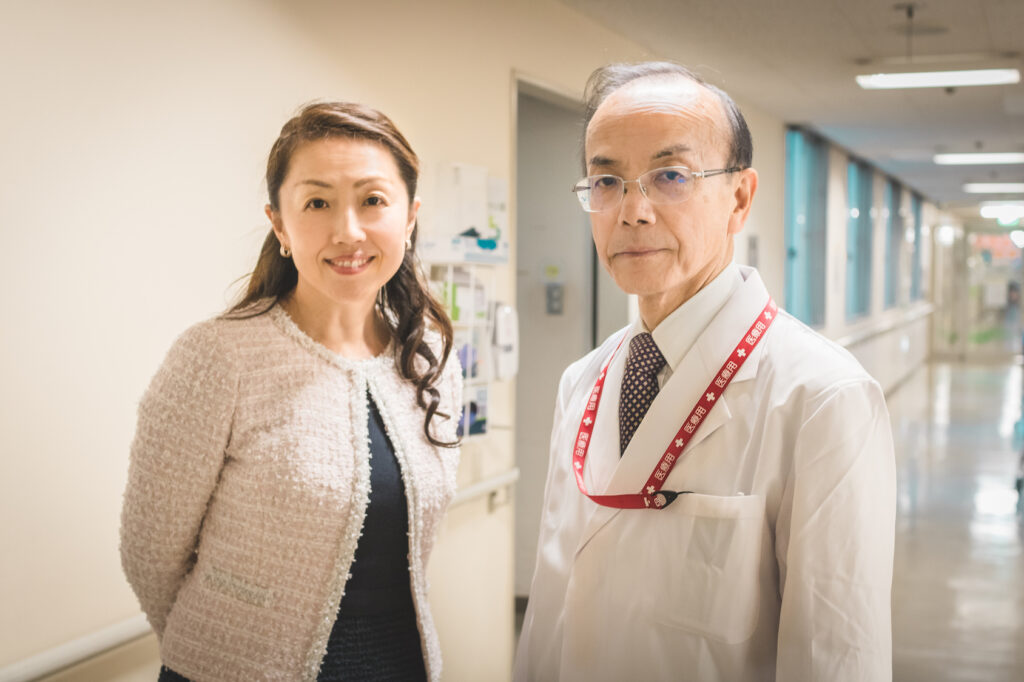
練馬区の急性期医療を支える
中:今回は練馬光が丘病院、名誉病院長の川上正舒先生にお話を伺います。
先生どうぞよろしくお願いします。
川上:よろしくお願いします。

中:まず、貴院の特徴を挙げてください。
川上:当院の歴史は約30年前に練馬区医師会立病院として設立されたことに始まります。
その後、日大が運営を引き継いでいたのですが、
諸事情で7年前に私たち地域医療振興協会が運営するようになりました。

現在、練馬区内には総合病院が二つあり、その一つが当院です。
練馬区は人口72万を数え、23区で最も新しい区であり今でも宅地造成が続いていて、
病院が不足しています。
急性期医療に対する区民の高い需要があり、当院にも強い期待が寄せられています。
特に寸秒を争うことも多い心血管病に関して力を入れていて、
急性冠症候群や大動脈瘤の治療については都内でも有数の症例数を抱えています。

東大の教育を変える情熱
中:ありがとうございます。
次に先生のご経歴を伺いたいのですが、まず医師になられた動機をお話しいただけますか。

川上:今の若い人の間では医学部進学が大変人気のようです。
しかし私たちの時代は日本が工業国家として急成長している時期で工学系の希望者が多く、
理系でありながら医学部を目指すのはむしろ少数派で、私の父も兄も工学系でした。

私には家族とは少し違う方向に進みたいという気持ちがあったのかもしれません。
また母親が病弱で私が小さい頃から入退院を繰り返していたことも、
医療に引かれる一因だったように思います。
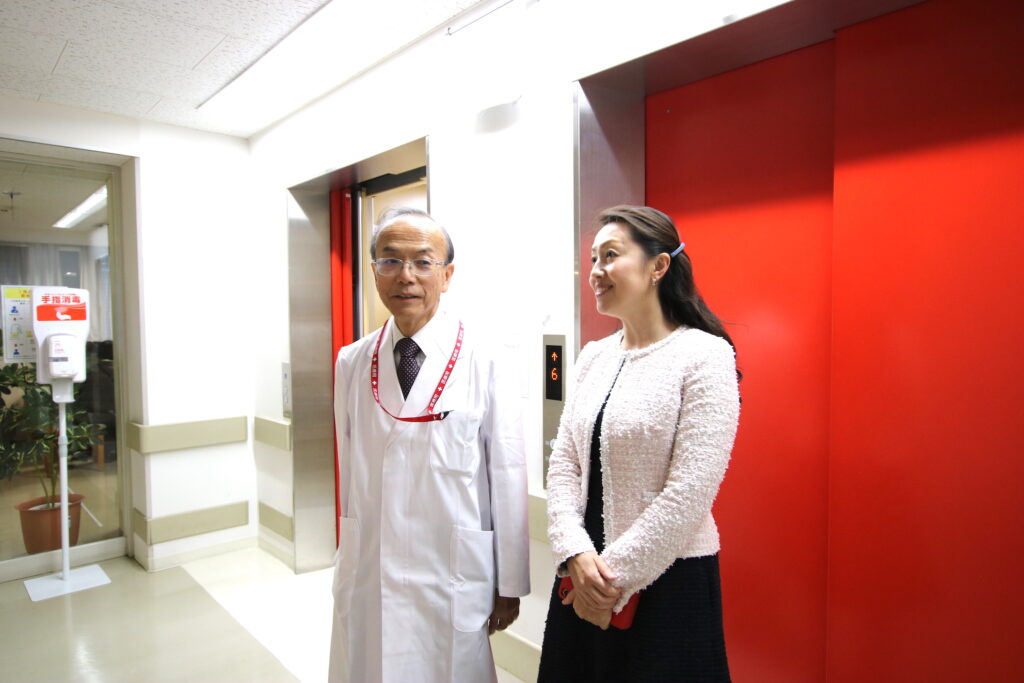
中:先生は東大ご出身と伺いました。
大学時代の記憶に残るエピソードをお聞かせください。
川上:東大は今もそうですが、1〜2年は教養課程で3年目から本格的な医学教育が始まります。
キャンパスも分かれていて最初の2年間は、工学や数学、生物学などに進む学生と机を並べて学びます。
いま考えるとそれが私にとっては大切な経験でした。
そのころの友人、つまり医者とは別の職業に就いた友人とは、いまだに親交があります。

また当時は学園紛争、東大の学生は「闘争」と言っていましたが、
医学部を発端とするその紛争の最中で、私自身も1年半ストライキをしていました。
それもまた克明に記憶に残っている思い出です。
紛争終了後は、学生も教える側も東大の長い歴史を何とか変えていこうという雰囲気の中、
すべてがトライアンドエラーのような授業形式で進められていました。

今の学生を見ますと「何を教えてくれるの?」という態度に見受けられ、
私にとっては「えっ、それでいいの?」という感じがあります。

糖尿病患者の「変なヘモグロビン」
中:ご卒業後にコロンビア大学やロックフェラー大学にご留学されていますね。
川上:そのころ日本とアメリカの医学には臨床も研究もかなり格差があり、
私もアメリカに対する憧れをずっと抱いていました。
そんな時、先輩から「帰国するから交代要員として来ないか」という話があり、
喜んでコロンビア大に留学しました。

当時、コレステロールが動脈硬化を起こすという「仮説」を証明するための研究が花盛りで、
その有力な研究室の一員として加わりました。
またコロンビア大の附属病院の内科にも参加し、幸いにも内分泌代謝領域を経験することができ、
その後につながっていきました。

中:その後、糖尿病をご専門とされるようになっていかれたのですね。
川上:2年半のコロンビア大在籍中に「糖尿病の患者さんには変なヘモグロビンがある」ということが
注目されるようになっていました。
当時は、生体内では酵素反応以外は起こらないと言われていた時代です。

このヘモルロビンは糖化されたヘモグロビンであり、後に血糖コントロールの指標として活用される
HbA1やHbA1cであることが判明してきたような状況でした。
それに興味をもちこの研究のメッカであったロックフェラー大に移りました。

エールリッヒ賞につながる研究
中:今でこそHbA1cは広く認知され糖尿病のスクリーニングや治療に必須の検査になっています。
先生は当時からその可能性を感じ、糖尿病治療に大きく貢献できるのではないかと
お考えでいらしたのでしょうか。

川上:そのころはそれほど高邁な理想があったわけではなく、単純に「面白いな」という動機です。
私がロックフェラーに行った時は、いま申しましたような基礎的研究は終わりに近づいていて、
次のテーマとしてグリケーション(タンパク質の糖化)がクローズアップされつつありました。

例えば目の水晶体が濁ると白内障になるわけですが、糖尿病では年齢よりも速く白内障が進みます。
その原因は水晶体のグリケーションによるとの仮説で研究が進められていました。
しかし、研究室では、その研究には既に多くの人が関与していて私の出る幕はなく、
全く別の感染症とインスリン抵抗性の研究をするように指示されました。

結果的に、インスリン抵抗性を惹起する内因性のホルモン様物質(現在ではサイトカインと呼ばれる)
であるカケクチン(現在ではTNFと呼ばれている)を発見し、その研究の重要性が評価され、
昨年、ヨーロッパで最高の医学賞と言われているエールリッヒ賞を、
私のボスのアンソニーセラミ先生が受賞しました。
1980年代の論文発表がいま認められたかたちです。
先生は授賞式の記念講演の中で、私の名前を二度も三度も言ってくれました。

研究者の姿勢と家族の支え
中:先生の発想と研究が受賞につながったのですね。

川上:特に私が何かをしたということではなく、ただ研究のことばかり考えていたということです。
海外での研究中の我が家は、俗な言い方をすれば「家族を犠牲にした家庭」だったと思います。
家内も大変だったと思います。
いま家内に尋ねると「苦には思っていなかった」と言いますが。

中:とても理解のある奥様ですね。
川上:研究生活の思い出話を若いドクターにしますと
「そんなことは、何も先生がやらなくても大事なことであれば、いずれ他の人が発見しますよ」
と言われます。
確かにそうなのかもしれませんが、研究者というのは自分の力で、
何か新しいことを見つけることを生きがにしている存在だと思います。

後編に続く
Interview with Carlos & Nakada