東京都西部の多摩南部医療圏にある府中恵仁会病院は、217床の地域医療支援病院です。
昨年、院長に就任された立澤孝幸先生に、先生のご経歴や病院の特徴をお尋ねしました。

数学的な医学のリサーチ
中:今回は府中恵仁会病院、病院長の立澤孝幸先生にお話を伺います。
先生、どうぞよろしくお願いいたします。
立澤:よろしくお願いします。
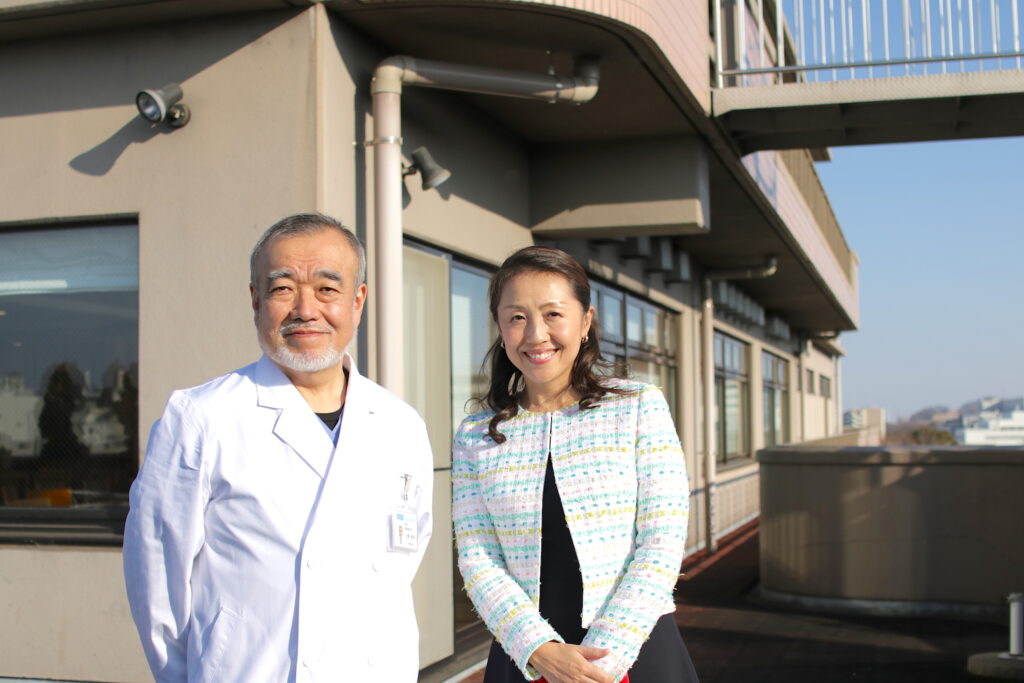
中:まず、先生のご経歴についてお聞かせください。
医師になられた理由はどのようなことでしたか。
立澤:私の実家は千葉で江戸時代から続いている商人の家です。
身近に医師を職業としている人はなく、私だけです。
と言いますのも、母親から「将来は兄弟みんな別々の職業につくように」と小さい頃から言われて育ち、
実際に母親の兄弟もそれぞれ異なる職に就いていたからです。
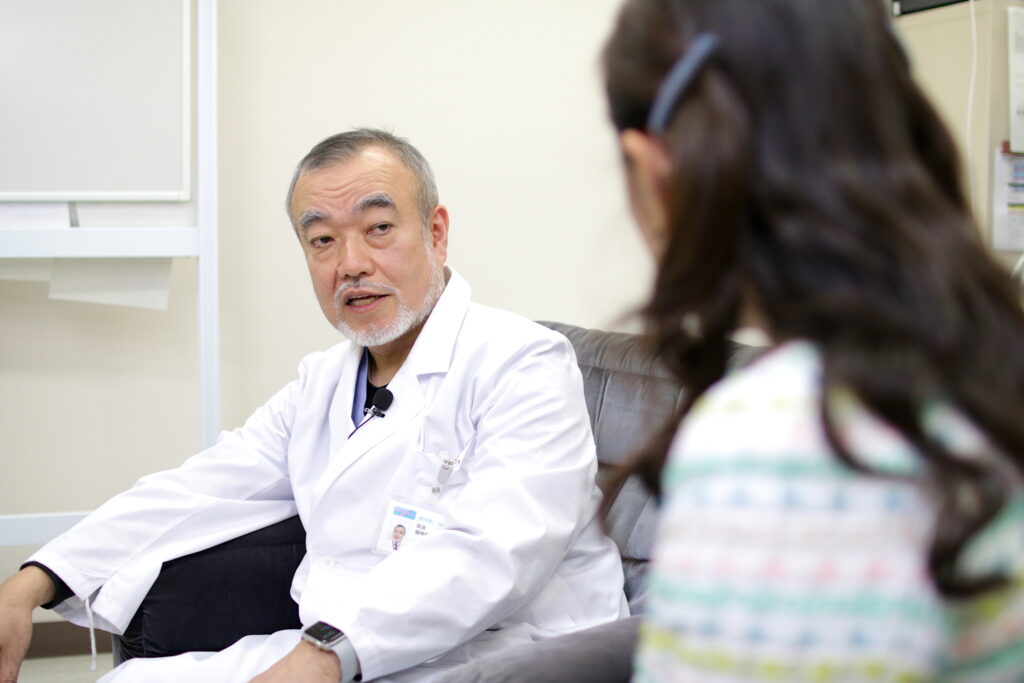
そのため高校時代には、かなり真剣にいろいろな職業を考えていました。
結果的に医師を選んだのは、子どもの頃に病気がちで、入院したり手術を受けたりしていたため、
他の子どもより医療の世界を身近に感じていたからだと思います。

中:医学生時代の思い出に残っているエピソードをお聞かせください。
立澤:日本医大は私大としては古くからある医科大学で、個性的な先生方が多かったです。
例えばテレビなどに出演されている数学者の秋山仁先生が数学科の助教授でした。

秋山先生は「数学を医療に持ち込み、数学的な発想を持った医療を目指す」という教育をされていて、
数理医学研究会というサークルを指導してくださっており、大型コンピューターで心電図の逆合成を行い、
学生でありながら学会発表を行ったこともありますし、
学生時代に数学の国際的ジャーナルに論文を発表した優秀な部員もいました。


数理医学研究会、ラグビー部、茶道部での活動
中:クラブ活動は何をされていましたか。
立澤:いま申しましたような学問的な系統では数理医学研究会というクラブに所属していました。
あとはラグビー部にも籍を置いていたことがあります。
少し変わったところでは茶道部にもいました。

中:茶道ですか。
素敵ですね。
立澤:中学高校で、江戸千家のお家元の弟さんと同級で、大学に入ってみたら彼のお兄さん、
すなわち江戸千家のお家元が茶道部の師範でしたのでご縁があって参加しておりました。

脳外科医を目指した理由
中:ご卒業の際、専門領域として脳外科を選択された理由をお聞かせください。
立澤:大学でラグビーをやっている時に同級生が試合中に頭部外傷で亡くなったのです。
その衝撃もあって私の学年では脳外科に進む者が比較的多く、私もその一人でした。

中:脳外科医としてどのようにキャリアを積んでいかれましたか。
立澤:当時はまだ大学の講座が第一外科や第二外科など大講座制の時代で、
私が卒業する頃にちょうど脳外科や心臓外科が独立し始めていました。
このような時代的な背景もあり、脳外科医として腕を磨くにはどこがいいかと考えた結果、
大学ではなく市中病院を選ぶことにしました。

具体的には、脳神経外科が早くから独立した診療科として存在し、日本医大脳神経外科の初代教授であった
近藤駿四郎先生が名誉院長で日本医大からうつられた杉浦和朗先生が部長をしていた東京労災病院でした。
杉浦先生は当時高名であった英国エジンバラ大学のギリンガム教授のもとに2年間留学されており、
世界で最初の意識障害の評価表であるエジンバラ方式を発表した先生です。
近藤先生は、クッシング現象やクッシング病、ダンディー・ウォーカー症候群にその名が残っている
クッシングとダンディーのもとで学ばれたこともある先生で日本の脳神経外科の始祖の一人です。

手術室はお茶室に似ている
中:脳外科の手術にはかなり精神的な集中力を必要とされるのではないかと思いますが、
いかがでしょうか。
立澤:そうですね。
ただ、手術に関してはどの診療科でも恐らく同じように緊張して行っていると思います。
私の場合、茶道でお茶を立てる亭主がお茶室の中の雰囲気を支配するのと同じような感覚を
手術中に感じていました。

手術室では執刀医が手術中の雰囲気をすべて支配していて、緊張はあるものの非常に充実した時間でした。
もっとも、手術室がお茶室と似ているなと思ったのは、
自分がメインの術者になれるようになってからです。

中:先ほど伺った茶道のお話が、大学時代のエピソードにとどまらずに
外科医になられてからも関係してくるとは思いませんでした。
立澤:中学や高校時代にやっていた剣道やボート競技も、
集中力やチームワークの涵養に役立っていたように感じます。
手術はやはりメンバーの息が合わないとスムーズにいかないのですね。
術者と助手の意思疎通が十分取れていると、
初めから終わりまで、ひと言も話さずに手術が終了しているように感じることもあります。

自分の理想の医療を追求してみたい
中:阿吽の呼吸で淡々と手術が進んでいくのですね。
なにか芸術的な感じがいたします。
引き続き、現在の院長職に就かれるまでの経緯をお聞かせください。
立澤:「ぜひ院長になりたい」と思っていたわけではありません。
ただ、長く臨床をしていますと恐らく多くの医師が、
自分なりの理想的な医療を追求してみたいという気持ちが芽生えてくるのではないでしょうか。
そして開業を選択する人もいるのだと思います。

私も勤務医時代に、やろうと思っていたことでできなかったこともあり、
病院をシステマチックに満足いくかたちで運営してみたいと思っていました。
そして以前勤めていた関東労災病院の定年に近づいた頃、何か所かからお誘いのお話をいただいた中から、
私自身、もう少し急性期医療を続けていたいという気持ちがあり、当院の院長をお受けすることとし、
昨年4月に就任しました。

中:インタビュー中にも救急車が何度か到着しているようですし、
こちらでも急性期医療に忙しくされているのではないでしょうか。
立澤:府中市で昨年1年間に救急車の出動が約1万7,000件あったそうです。
当院は多摩南部医療圏の南端で多摩川を界に南多摩医療圏と接している関係で
府中市以外からの救急搬送もあり、当院には年間約5,000台の救急搬送があります。
平成30年度で言えば3月末までに6,000台近くに到達すると予想しております。

中:たいへんな数ですね。
ここで、貴院の特徴を挙げていただけますか。
立澤:当院の救急指定は2次救急です。
重症患者は3次救急である都立多摩総合医療センターや日本医科大学多摩永山病院と連携して
診療にあたっております。
一般病棟151床、地域包括ケア病棟34床、回復期リハビリテーション病棟32床、
合計217床という病棟構成です。

地域医療支援病院として開業医の先生方と連携して地域医療を支えていく使命があります。
200床以上が地域医療支援病院の基準ですから、当院の217床という規模は、
地域医療支援病院として日本で一番小さいくらいの規模ではあります。
しかし、とにかく設備や人員を充実させて地域医療に貢献したいと考えております。

後編に続く
Interview with Toan & Carlos




