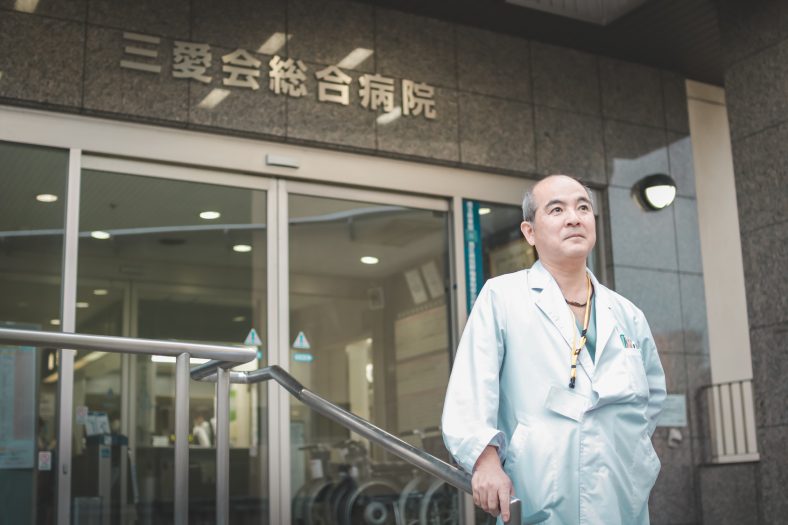前編に続き清水先生に、看護師へ期待することなどのメッセージをいただきました。
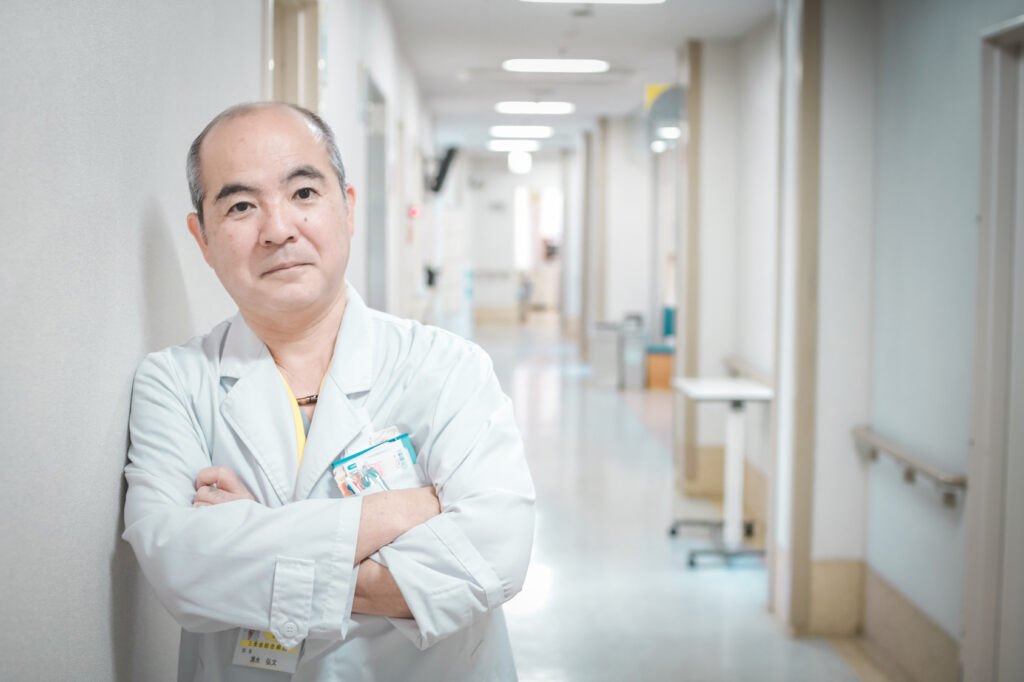
疾患の深い理解をベースにした看護に期待
久保:ここで看護師について伺います。
先生はいま看護師にどのようなことを期待されていらっしゃいますか。
清水:どのような疾患も、異常の早期発見が鍵となります。
我々医師は24時間365日、患者さんの側に寄り添うことはできません。
それができるのは看護師です。
その点は看護師という職業の素晴らしさです。

ただし私は「看護」というものは、疾患の深い理解を基盤としなければ
成立しないものではないかと思っています。
患者さんの側にいて
「この患者さんは何かおかしい、いつもと違う」とか「自分たちの手に負えない」と判断し
ドクターコールするには、深い理解がないとできないことです。

もう少し具体な例を挙げますと、入院患者さんが熱発したとき
「先生、誰々さん熱が出ています。どうしたら良いですか?」と聞くのではなく、
「こういう機序での発熱と考え、このように対処しました」と言える看護師に
なっていただきたいところです。
もちろん法的に「看護師は医師の指示のもとで診療の補助行為をする」とされていますから、
事前に対処法も含めて指示を出しておくなどの措置は必要ですが。

久保:さきほど「最近の若い医師は救急受入要請を断る傾向がある」というお話がありましたが、
最近の看護師はいかがですか。
かつての看護師から何か変化していることがあればお聞かせください。
清水:いま申しました疾患に対する深い理解とリンクするのかもしれませんが、
薬剤の名称や機序に関する知識が低下しているのではないかと感じることがあります。
かつての看護師は、他院から紹介されてくる患者さんに処方されている薬を見れば、
その方の疾患名や重症度をおよそ把握できましたし、
自分が知らない薬剤は「医薬品集」を調べるといったことをしていました。

ところが今は、薬剤に関してはほとんど薬剤師に丸投げしてしまうケースが増えていないでしょうか。
本来、薬は疾患のcureにもcareにも深く関係することですから、看護師がそれに積極的に関わらない
というのはあまり良くない状況ではないかとの危惧があります。

久保:それは医薬分業の推進によって生じた変化なのかもしれませんね。
一方で専門看護師や認定看護師などの資格を有する看護師が増えつつあります。
この変化を先生はどのようにご覧になっていますか。
清水:ある領域の専門性に特化した看護師が増えるのは歓迎します。
ただ、専門性を高める基盤として、看護全般に共通する知識や技術を身につけているべきだと思います。

7対1加算は目標ではなく、看護を充実させている結果
久保:専門領域以外の看護はおぼつかないというのでは困ってしまうということですね。
看護師についての先生のご意見を多々お聞かせいただきましたが、医療全般について
先生は今どのようなことに関心を持たれていますか。
清水:行政主導での「病院から在宅へ」という流れがありますね。
我々のような急性期病院では平均在院日数や看護必要度の評価、在宅復帰率など、
算定要件が年々厳しくなっています。

この流れは間違ってないと思います。
しかし、病院で提供する医療がこのように変化しつつあることを、もっと社会に啓発してほしいと思います。
一般の人々にはまだ「病人を家でみる」という発想がないのですね。
ですから「まだこんな状態なのになぜ退院させるのか」という話になってしまいます。

また、患者さん本人が家に帰りたいと希望しても、家族が介助や介護をできないということもあります。
特に老老介護や独居高齢者ではこの点がしばしばネックになり、行き場のない患者さんが出てきます。
資産がある人はサ高住での生活も可能かもしれませんが、
生活保護を受けなければ退院できない方もいらっしゃいます。
今の日本が格差社会であることを痛感しています。

久保:すぐには解決できない難しい問題ですね。
清水:「1億総活躍社会」との掛け声がありますが、
こういう方たちを誰がみていくのかということが大変気になります。
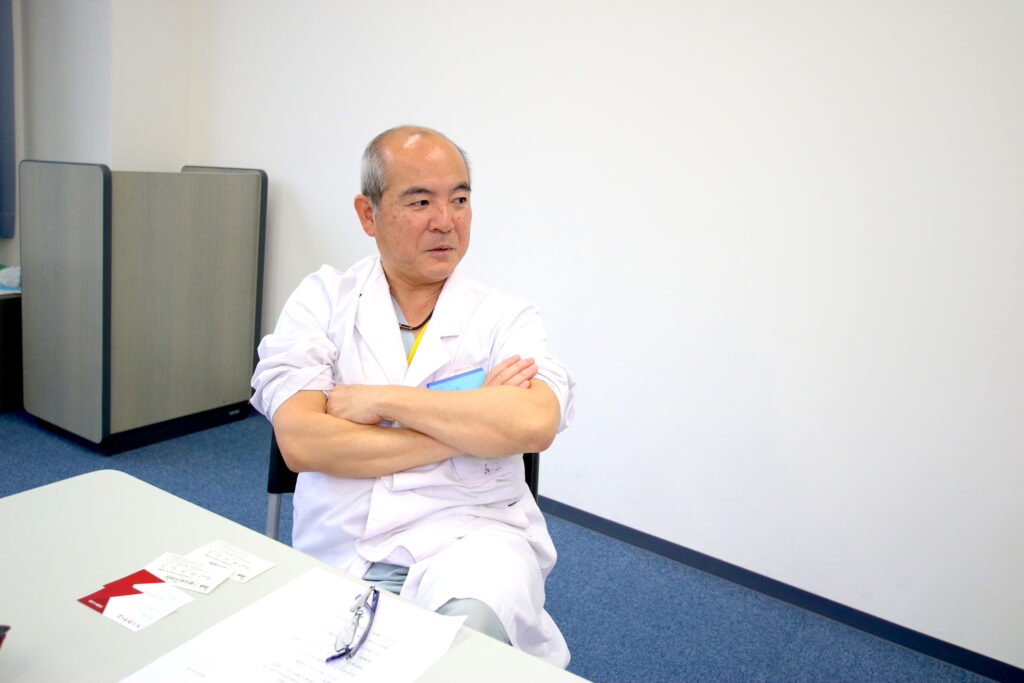
久保:医療や社会がそのように変化していく中で、先生は貴院をどのように
舵取りしていこうとお考えでしょうか。
清水:先ほども少し申しましたが、医師にとって魅力のある病院を目指し、
それによって魅力のある医療を提供し、
埼玉県東部医療圏のニーズに応えていこうという発想で動いています。
看護基準は現在7対1体制をとっています。
これは目標にするという性質のものではなく、医療・看護を充実させた結果として
後から付いてくるものだと理解していますが、できれば今後も維持・継続していきたいところです。

新築・増床時に中核を担える看護師を募集中
久保:最後に先生のご趣味をお聞かせください。
清水:趣味はこれといってありません。
働くのが趣味ではありませんが、心身ともに健康であるように気を付けています。
自分が体調不良では、人を診ることはできませんから。
スッタフにも心身の健康については、事あるごとに説いています。
強いて言えば趣味は、適度に酒を飲むことと、たまにラウンドすることくらいです。

久保:では、看護師へのメッセージをお願いします。
清水:病院という組織は看護師がいないことには成り立ちません。
当院では看護部長が先頭に立って、どんな人にも働きやすい条件を整えてきました。
その効果だと思いますが、以前は年に一桁だった新規入職者が今では十人以上に増えています。

当院は、住所は埼玉県ですが実際は東京のすぐ隣に位置します。
また、現在の建物はだいぶ古くなっていますが数年以内に移転・新築・増床します。
その時に看護業務の中核を担っていただけるような看護師さんに、
ぜひ今から当院で働いていただければいいなと思っています。

インタビュー後記
お話しの最中、微笑みを絶やさない清水先生の他者への優しさを感じたインタビューでした。
「ドクター同士、あるいは、ドクターと看護師が互いにプロとして敬意を払うことが、病院の雰囲気を良くしていくために欠かせない」とおっしゃる先生の期待に応えるためにも、
看護師は常により良い看護を目指して進化し続ける必要あるのかもしれません。
地域の発展とともに歴史を刻んできて、さらに数年後の移転時には
大幅に増床する可能性があるという三愛会総合病院。
これからの発展が楽しみです。

三愛会総合病院関連記事
Photo by Carlos