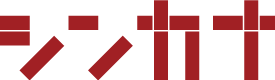南多摩病院の院長、益子邦洋先生は、国内にドクターヘリを普及させた先駆者の一人です。
インタビューの前編では、その歴史の興味深い裏話もお伺いすることができました。

父の往診に同行して
中:今回は、南多摩病院、院長の益子邦洋先生にお話を伺います。
益子先生、まずは貴院の特徴を挙げていただけますか。
益子:当院は170床の二次救急病院です。
救急医療と高齢者医療に非常に力を入れております。
それらに加え、昨年には骨折・手外科センターという専門部門を開設し、
常勤医・非常勤医11人体制を敷いています。

中:ありがとうございます。
では次に、先生のご経歴についてお伺いしたいのですが、
医師になろうとされた動機はどのようなことでしたでしょうか。
益子:父が医師でしたが、自分自身は高校時代、当時人気のあった電子工学領域へ進もうと考えていました。
父と私は年齢が42歳離れていて、その頃すでに60を超えていました。
しかしそれでもしばしば患者さんに請われて夜中に自転車を漕いで往診に出かけていました。
それが大変そうでしたので、私が軽自動車の免許をとり(当時は16歳から軽自動車免許を
取得できました)、往診に向かう父をスバル360という小さな車に乗せて行くようになりました。

患者さん宅で父が診察している間、私は隣の部屋で待機しています。
すると、患者さんやご家族と父との会話が聞こえてきます。
深刻な話の時もありました。
そういった父の対応を見聞きしているうちに「医師という仕事は大変だ。しかし、とても大事な仕事だ」
という思いが募ってきて、急遽方針を変更して医学部を目指しました。

外科から救急医療へ
中:医学生になられた後、ご自身の専門科をどのようなプロセスで選んでいかれたのでしょうか。
先生は救命救急医療でご高名ですが、初めからその領域にご興味がおありだったのですか。
益子:当初は外科全般に興味があり、母校の日本医大に新設された第三外科学教室に入りました。
胸部を中心としつつも全身の外科を手がける教室です。
その第三外科で5年ほど研鑽を積んだ頃、日本医大に三次救急医療を担う救命救急センターが設置され、
1年間という期限付きで私が出向することになりました。

行ってみて驚きました。
広範囲熱傷の患者さん、心臓を刺された患者さんなど、寸秒を争う患者さんが搬送されてきて、
直ちに緊急手術を行い救命するといったことの連続でした。

待ったなしの現場で外科医として腕を振るうことにやりがいを感じ、1年で戻るのは「もったいない」と思い
2年に延期してもらい、2年たつとさらに面白くなってまた延期してもらいました。
ついに第三外科の医局では「あいつはもう帰ってこない」いうことになり、
救急医として進む道が固まりました。

中:救命救急はもちろん大変お忙しいと思います。
それを上回るやりがいがあったということでしょうか。
益子:そうです。
「きつい」のは当然ですが、やりがいはそれをはるかに上回っていました。
死に瀕していた患者さんが手術と集中治療によって元気に社会復帰していく姿は、
なにものにも代えがたい喜びです。
結局、日本医大の千駄木の本院で19年、千葉北総病院で17年、あわせて36年間、
救命救急センターに勤務しました。

ドクターヘリの先駆け
中:都区内の千駄木と千葉北総とで、救急医療体制に何か違いがおありでしたか。
益子:日本医大の千駄木に救命救急センターができた頃は都内に同様の施設が少なく、
都内全域から患者さんが搬送されてきました。
しかしその後、都内で30箇所近くまで施設が増え、
千駄木に搬送されてくるのは近隣の患者さんが中心となっていました。

ところが千葉の北総は東京とは全く違った状況で、非常に広大な範囲から患者さんが送られてくるのです。
当然、搬送に時間を要し、救命率の上昇にも限界がありました。
私は「ここではヘリコプターを使わなければいけない」と強く感じました。
と言いますのも、私がかつて留学していた米国のメイヨークリニックで、
ヘリコプターによる搬送を行い確実な効果を上げている状況を目にしていたからです。

中:それでドクターヘリの導入を進められたのですね。
益子: 2001年に厚労省がドクターヘリ事業をスタートし、全国で5施設が参加しました。
日本医大千葉北総病院もその一つです。
ところがそれ以降、他院にはなかなか普及しませんでした。

年間2億円と言われる維持・運営コスト負担の問題だけでなく、医療者側の無理解もありました。
「日本は道路網がしっかりしているからヘリは必要ない」「もしヘリが落ちたら大変だ」「うるさい」などと
よく言われたものです。

そのような状況を一変させたのが、警察庁長官をされたことのある國松孝次さんです。
國松長官が狙撃され瀕死の重傷で千駄木の日本医大に搬送された時、私と私の上司とで手術をしました。
そのとき私の頭の中にあったのは、世界の外傷外科医の中で「ゴールデンアワーストラテジー」
と言われていた「受傷後1時間以内に根本的治療を行う」ことです。

そして長官は無事退院され、公務に復帰されました。
その体験から國松さんは救急医療の重要性を認識され、
後に「ドクターヘリ特別措置法」の制定に向けて尽力してくださいました。

中:ドクターヘリを一気に増やすには機体やヘリポート確保以外に、
ヘリに乗るフライトドクターやフライトナースの育成も必要かと思います。
その仕組みやコストはどのようにされたのでしょうか。
益子:それには面白い逸話があります。
國松さんが東大在学中のころ剣道部に所属されていて、そこには後にトヨタの会長になる張富士夫さんも
いらっしゃり、二人で副主将と主将を務める関係だったそうです。

國松さんからコスト面の相談を受けた張さんは、経団連で有志を募って
「ドクターヘリ普及促進懇談会」を立ち上げられ、皆様からのご寄付を財源として
ドクターヘリ搭乗医師・看護師等研修助成事業を始めてくださいました。
医師・看護師の育成が進むにつれ、急速にドクターヘリの全国網が完成していきました。

コード・ブルー
中:やはり、ドクターやナースの誰もがすぐに、
フライトドクターやフライトナースとして活躍できるわけではないのですね。
益子:ヘリでの搬送対象となるのはすべて「待ったなし」の患者さんです。
脳卒中、心筋梗塞、広範囲熱傷、重篤な外傷など、
あらゆる事態に臨機応変に対処できる知識と技術を身につけている必要があります。

中:先生はテレビドラマ「コード・ブルー」の医事監修もされていましたが、
それもある意味で啓発活動になっていたのではないでしょうか。
益子:テレビの影響は甚大です。
私もドクターヘリの重要性を全国各地で講演することがあるのですが、
聴衆がどんな多くても数百人規模です。
ところがテレビでは数百万人が見るわけです。

「コード・ブルー」の放映後、「フライトドクターになりたい」という医学生や
「フライトナースになりたい」という看護学生が増えました。
ヘリを運用している会社には、「ドクターヘリのパイロットになりたい」という入社志望者が
増えているそうです。

中:先生が長年めざしてこられた救急医療の一つのかたちが日本に根付いたと言えそうですね。
益子:感無量です。
中:まだ実現できていない医療上の課題はございますか。
益子:まだまだたくさんあります。

例えば、在宅あるいは介護施設で療養中であり、既に予後改善の見込みが少ないことを
主治医だけでなくご家族や介護スタッフも理解している患者さんの容態が急変し、
救命救急センターに運ばれて来ることが少なくありません。
到着時に心肺停止状態でも、搬送されてきた以上は蘇生を試みます。
すると再び心臓が動き出すことがあります。
ただしほとんどの場合そのまま意識は戻らずに長期間の集中治療が必要になります。

私は、このようなケースへの対応は三次救急病院ではなく、患者さんやご家族により近い存在である
二次救急病院の方が適していると考え、二次救急病院の先生方に、そのように訴えてきました。

後編に続く
Interview with Toan & Carlos