前編に続き職員満足度の重要性や2025年問題についてお話しいただきました。
職員満足
職員連携のために取り組まれていることを教えてください。

職員が満足して勤務できなければ、患者さんの満足は得られない。
つまりエンプロイー・サティスファクション(Employee Satisfaction; ES)がなければ、カスタマー・サティスファクション(Customer Satisfaction; CS)なしということを伝えています。
病院はそのために何を実践すべきか?
具体的は外部の会社に依頼し、講習会を行なうことや、接遇委員会などで情報交換も行なっています。
そして、優れた職員についてはベストスタッフ賞を設けて年2回表彰しています。

また、レクリエーションも実施しています。
職員が500人ほどの時は大体の顔と職種がわかりましたが、現在のように1000人以上になると、職員であることは分かっても職種はまではわからなくなります。
そこでコミュニケーションをはかるため、各部署からメンバーを募り担当の委員会を設置し、年1回、勤務後に室内で玉入れ競争を行うことになりました。
今年で3年目になります。1チーム20人以上で、必ず多職種がメンバーにいることを条件にしました。
1日目は予選、2日目は決勝の2日間行い、前回は20数チーム、総勢450人ほど参加しました。
優勝すると互助会から景品が送られる特典付きです。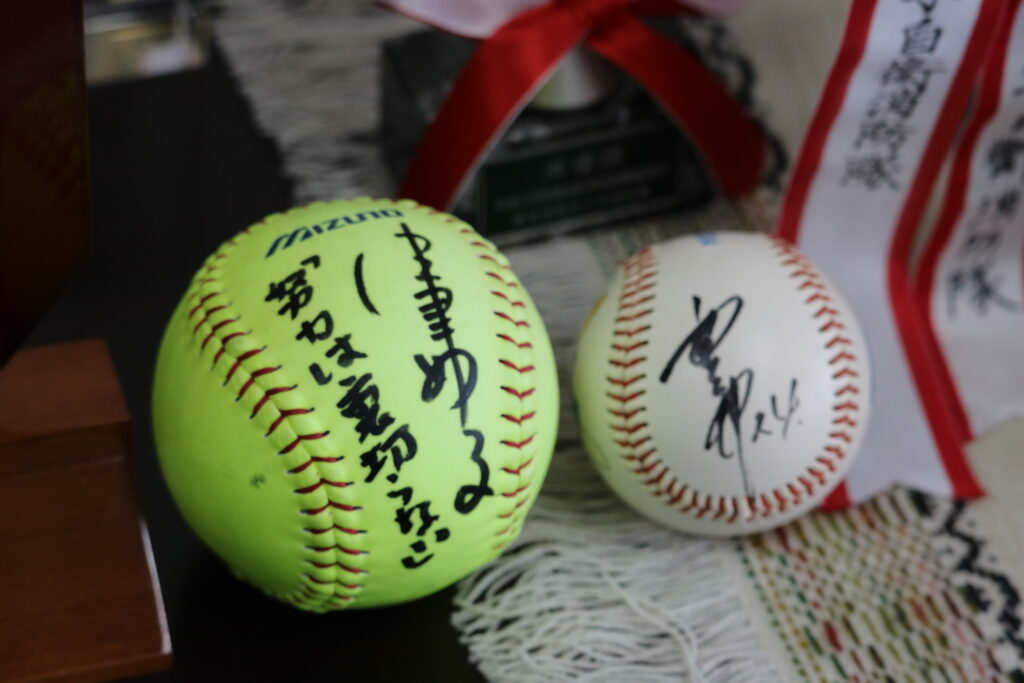
 (女子ソフトボール監督の宇津
(女子ソフトボール監督の宇津
それを機に、「じゃ、飲み会やろうか」と、雰囲気が良くなっています。
病棟回診は、月2回ほど行い、病棟へ行き、看護師や患者さんに直接声かけをしています。
看護師の教育システムがしっかりしていて、新人の看護師の離職率が全体の6%前後です。
看護師の負担軽減、PNSへの取り組みや院内のチームワークの改善により、以前の3倍の応募がかかるようになりました。
情熱を持った看護師が入職すると、病院の雰囲気も良くなります。

2025年問題について
2025年問題についてお聞かせください。
上西:救急患者が多く来院し、救急車だけで年間に8,000台ほど来ます。
そのため高度急性期病院として運営すると決めています。この地域は、北多摩北部の二次医療圏になります。
5つの市があり、全部で41病院が存在します。
41病院と5つの医師会が集結し、連携協議会を設置し、様々な問題を検討して地域の結束を強化しています。
年2回ほど会議を実施しており、1回目は幹事病院と各市医師会長が集まり情報交換を行い、2回目は総会と講演会を行ないます。

連携協議会の下部組織として、事務職やMSWなど100人前後集まり、お互いに医療情報交換を行なう連携職会議があります。
それにより、患者さんが転院する際、スムーズに行うことが出来るようになりました。
また、今年度から薬剤耐性菌に関連する連絡会議を設置し、地域内で情報交換を行なうことを開始しました。
さらに、高齢者増加による、食事形態や栄養の問題を検討するために、この地域で、栄養管理やバラバラな食事形態の認識を合わせる部会を立ち上げて、今後ディスカッションしていく予定になっております。
北多摩北部の二次医療圏内で500床規模は当病院しかありませんので、中心となって情報交換を行い、患者さんと高齢者をスムーズに入退院できるように取り組んでいます。

今後の更なる構想はありますか。
上西:まずは大きな目標である、患者さんと職員に選ばれる日本一の自治体病院を目指して頑張りたいと思います。
また、地域連携の推進のために、連携協議会を発展させNPO法人にするなど、社会的にも認められる組織にし、尚且、きちんと活動をすることです。
地域医療構想は二次医療圏が中心になって行うことになっています。
この周辺地域はJR中央線により、南北に分けられているので南側からは患者さんがあまり来院しません。
しっかりとした患者さんのケアをするためにも、二次医療圏を超えて当院のミッションである高度・急性期医療を担っていきたいと思っています。

看護師へのメッセージ
上西:当院は「看護師さんは病院の宝です」と謳っています。
実際にその言葉を見聞きして入職した看護師もおり、頑張っています。
やはり病院の最大の勢力は看護師です。
看護師が楽しく働けば、患者さんにとって良い看護が可能になります。
それを考慮し病院の方針を決め、様々な教育システムを採用しています。
認定看護師や専門看護師の取得をサポートする体制も構築しています。
今後は「特定行為に係る看護師」が非常に重要になりますので、今後より一層育成に力を入れていきたいと思います。
看護師の仕事を大事に考えている病院ですので、ぜひいらしていただければ有り難いです。

シンカナース編集長インタビュー後記
外科の先生ならではの手術のお話から、経営改善、それも億単位の赤字が出る可能性に立ち向かわれたお話まで上西先生には多くを語っていただきました。
職員一丸となって結果を出し、チームワークを維持するためのアクティビティも積極的に実施されている。
職場の人間関係が良いからこそ創り上げることが出来る未来があると実感させていただきました。
一方で、何もせず職場環境が良くなるわけもなく、病院長自らアイデアを出され、職員間のコミュニケーション向上のシステムを構築されていらっしゃいました。
病院でも、とうとうESがいかにCSに結びつくかということを意識されて経営を行うリーダーが出たのだと驚きました。
ビジネススクールや、一般企業ではよく聞く言葉でしたが、病院から聞くことが出来る時代の到来を嬉しく感じました。
病院にも経営は存在し、医療職であっても治療を行うとことだけに集中すべき時代ではないのだと学ばせていただきました。
継続出来るシステムを作り上げることもリーダーの役割であり、スタッフ全体を巻き込んで実現された上西先生を心より尊敬いたします。
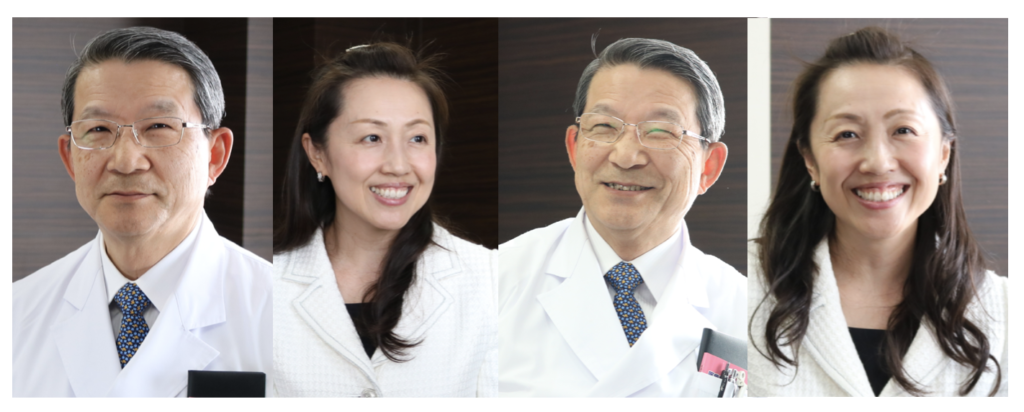
公立昭和病院関連記事
Interview Team




