前編に続き、甲能先生に耳鼻科の魅力や、看護師に進化して欲しいこと、院内チームワークの良さなどお話いただきました。

医療環境とともに変化が求められる看護師像
耳鼻科の魅力を教えてください。
甲能:首から上の脳以外は診断、治療、手術まで全てを耳鼻科は行うという点です。
内科は、診断後に手術が必要なら外科に回します。
耳鼻科医は内科的なことも外科的なことも扱います。
さらに感覚器を扱いますから治療後のQuality of Life(生活の質)も考えなくてはいけない。
これからの医療は感覚器の機能をいかに維持させるかが大切です。
それを可能にするのは、臭覚や味覚、発声などを診て治療できる耳鼻科の医者ではないでしょうか。
患者さんと接していて非常にやりがいがあり楽しい診療科です。

以前は医師も60歳を過ぎて、目が悪くなると手術をしなくなる耳鼻科医が多かったのですが、
今は顕微鏡があるので外科医としての寿命も延びています。
そしてこの技術の進歩というものが医療教育に与えた影響も非常に大きいことは事実です。
何名かでオペに入り、同じ術野を4Kや8Kの精細な画像として同時に見られるということは、
医師を育てるという面でも大きな進歩と言えます。

看護師に進化して欲しいことは何でしょうか。
甲能:超高齢化社会になっていくと、医療・看護における看護師の役割は非常に大きくなると思います。
そういう時代が来るからこそ「優しい看護師さんであって欲しい」ということです。
思いやりを持ち、看護を実践していただきたい。
看護師が朝「おはようございます」と病室に入り患者さんと挨拶を交わすというだけでも、
患者さんにとっては嬉しいことだと思うのです。
そういう心配りができないと、患者さんも暗い気持ちになってしまいます。

今後は認定看護師やナースプラクティショナーに対するニーズがさらに増えてくると思います。
当院にもナースプラクティショナーが1名おり、
脳外科や麻酔科の先生と共に行動し、医師の負担軽減につながっています。
制度的なこともあり今すぐは無理かもしれないですが、5年、10年先には
こういう人たちの活躍の場がかなり広がるのではないでしょうか。

病院の特徴を強みにする
貴院の強みを教えてください。
甲能:健診部門に非常に広いスペースを取り、機器も充実させています。

また、内科の内視鏡関連は大学病院のドクターが驚くほどの設備が揃っています。
「内視鏡センター」というセンター化した組織をいま構築しているところです。
私の専門の耳鼻科では、内視鏡を使った手術もかなり進んだ方法で、きれいな術野を確保し手術を行っています。
これも大学病院のレベルだと思います。

院内チームワークの良さとアメニティを生かして
甲能:大学病院に比べれば小さな病院ですから診療科の垣根がなく、
何か頼むときに頼みやすいというメリットがあります。
患者さんを診ていて「ちょっとここおかしそうだな」と思うと、
別の診療科の先生に診てもらうというようなことが、フットワーク軽くできます。
さらに大学の放射線診断部の先生が常駐しておりますので、画像所見をチェックし、
何かあればすぐに各診療科へ確認の指示を出しています。
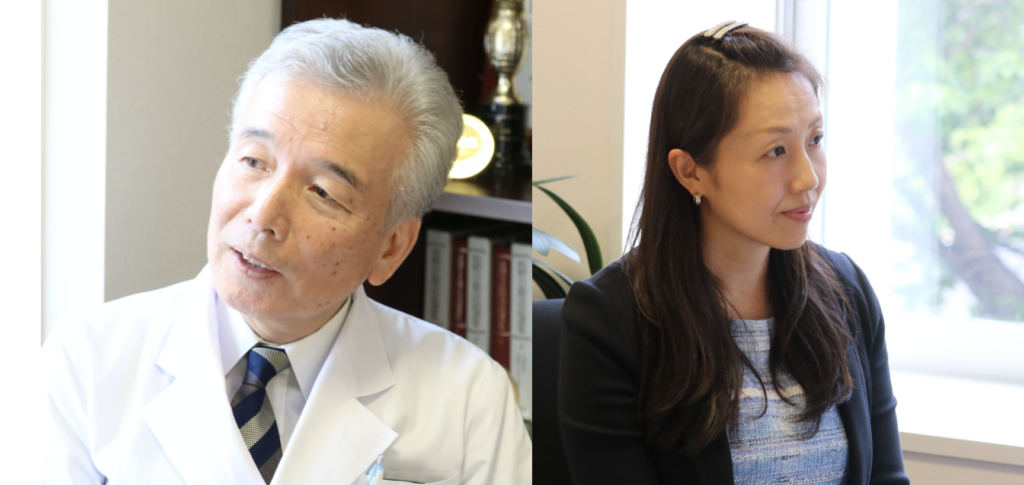
実際に微細な画像所見を放射線専門医が確認し、消化管穿孔を早期に発見し処置し得たという経験もあります。
各科の連携が非常に取りやすく、横断的で精度の高い診療が行いやすい環境も特色と言えます。
屋上に庭園を設けられているなど、アメニティ環境も素晴らしいですね。
甲能:屋上庭園の他、特徴的な設備として、大ホールが挙げられます。
大ホールではプロの音楽隊を招致しコンサートを行うこともあります。
外来患者さんはもちろん、病棟からも入院患者さんがベッドのまま参加され
「こんな素敵な音楽を聴けるとは思わなかった」と涙を流す方もいらっしゃいます。

こうしたイベントや医療安全教育などの企画へ職員が積極的に参加することも当院の特色です。
患者さんが急変して倒れた時に院内放送でスタットコール(手のあいているスタッフは全て集まれとの指示)
がかかることがあるのですが、迅速にみんな集まってくれます。
そういう意味では良い連携が保てているのではないかと思います。

看護師へのメッセージ
甲能:これから日本はますます高齢化が進むことが明確です。
医療や介護の分野で看護師が必要とされる場が非常に増えてくると思われます。
今後、現場で看護師の皆さま方に対する期待も非常に増えてくるでしょう。
そのときに、知識や技術の向上に加えて、患者さん、そして介護をする人に、
常に優しく明るく、相手に良い感じを与えるような対応をしていただければ、
患者さんも周りにいる家族の方も、たいへん心が休まると思います。
どうか、そういう優しい看護師さんでいて欲しいと思いますし、なっていただきたいと思います。
期待しております

シンカナース編集長インタビュー後記
超高齢化時代にニーズの高まるであろう看護師にこそ、優しくあって欲しいとおっしゃられた甲能先生。
病院内を見学させていただきましたが、新しく清潔な環境の院内は、歩いているだけで気持ちが良くなります。
また、スタッフの方々がとても笑顔に溢れていらっしゃることも印象的でした。
やはり施設が新しいということはハード面は充実しています。
一方で、甲能先生の推奨される「優しく明るい」看護師というソフトが充実していなければ病院としての完成は無いのだということも痛感いたしました。
今後、看護師が担う課題を改めて考えるきっかけとなるインタビューでした。

佼成病院関連記事
Interview Team




