湘南・藤沢で開院15年目を迎えたクローバーホスピタルは、
地域包括ケア構想を先取りした医療を展開してきているようです。
院長の鈴木勇三先生に病院の特徴や先生のご経歴を伺いました。
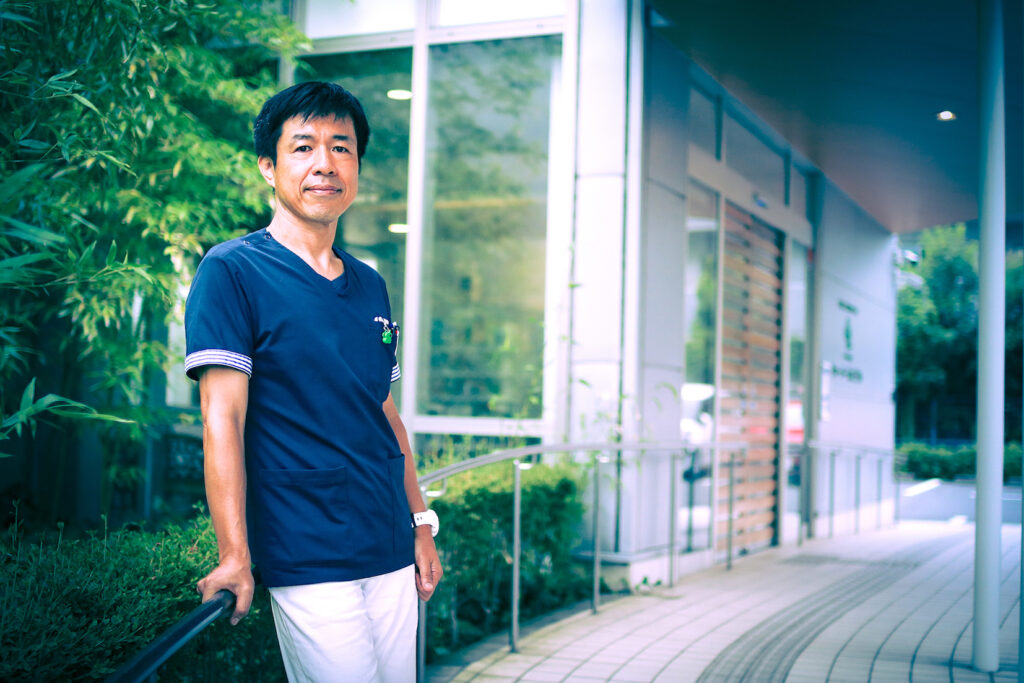
開院当初から地域包括ケアの一翼を担う
嶋田:今回はクローバーホスピタル院長の鈴木勇三先生にお話を伺います。
先生どうぞよろしくお願い致します。
鈴木:よろしくお願いします。

嶋田:最初に貴院の特徴をお聞かせください。
鈴木:当院は今年が開院15年目に当たります。
開院当初からあえて急性期医療ではなく、
地域の急性期病院と在宅医療、医療と介護を結ぶという立ち位置で続けています。

嶋田:後ほどその辺りの特徴をもう少し詳しくお聞かせいただきますが、
まずは先生が医師になろうとされた動機を教えていただけますか。
鈴木:父親の実家が代々、医師の家系だったことが大きいと思います。

先祖は源頼朝の侍医
嶋田:何代ぐらい医師が続いている家系なのでしょう。
鈴木:だいぶ続いています。
ご先祖様は源頼朝の侍医でした。
実家は頼朝が流罪された伊豆にあります。
ただ、父親は医師でなく、父の兄が医師だったのですが台風に被災し亡くなってしまい、医師の系統がいったん途絶えていました。
そういった話を聞かされて育つうちに、医師という職業に次第に興味を持つようになっていきました。

嶋田:医学部に進まれてから何か思い出に残るエピソードはございますか。
鈴木:大学は山形でしたので冬はスキー、雪がない季節はテニスをしていました。

嶋田:スポーツがお好きですか。
鈴木:そうですね。
スポーツは大好きで、今はひたすら走っています。

医師は自分が健康でなければいけない
嶋田:マラソンでしょうか。
鈴木:トレランといって山を走るレースです。
ウルトラトレイルという山の中を100㎞ほど一晩かけて走るレースにも月1回出ています。

嶋田:月1回とは凄いですね。
では普段から鍛えていらっしゃるのでしょうか。
鈴木:はい。
当院は急性期病院ではないので年配の職員が多いのではないかと思われるかもしれませんが、
実は常勤医10人の平均年齢は40歳前後です。
まだバリバリの若い医師が多く「医者は体力勝負」と言って、
みんな筋トレをしたりプロテイン飲料を飲んだりしています。
なにしろ自分が健康でなければ、患者さんが納得する話をできませんから。

呼吸器を目指した理由
嶋田:患者さんへの説明の一助として身体を鍛えていらっしゃるのですね。
もっとスポーツのお話をお聞きしたいのですが、話題を先生のご経歴に戻しまして、
ご専門領域をお決めになられた頃のことをお聞かせいただけますか。

鈴木:私は呼吸器とアレルギーを専門としてきました。
きっかけは大学6年生の時に実習先の病院で、
30代前半で末期の肺癌の患者さんを担当させていただいた時のことです。
リンパ管に沿って癌細胞が浸潤する癌性リンパ管症のため血液の酸素化がされず、
いくら呼吸管理を工夫しても低酸素血症が改善されない病態で、
癌の末期でも最も患者さんを苦しめる状態でした。

その患者さんを担当し、人にとって呼吸ができないことほど辛い事はないことを痛感し、
呼吸器を志しました。
大学を卒業し研修期間が終了した後は横浜市立大の大学院で喘息の研究に携わりました。
喘息では、ふだんは普通に生活している人が突然発作で苦しみ、時には亡くなることもあります。
その急変の機序が不思議だったのです。

嶋田:呼吸器やアレルギーの診療に、どのような魅力をお感じになられますか。
鈴木:呼吸器疾患と聞いて、みなさんがどのようなイメージを持たれるのかわかりませんが、
実は一般内科を受診される患者さんの最も多い主訴は「咳」です。
しかも咳の診断・治療は容易でなく、
慢性咳嗽のためにドクターショッピングを繰り返している患者さんも少なくありません。
ですから実臨床において、咳をしっかり診て治療することは非常に大事なことだと思っています。

誤嚥性肺炎への対応は国民全員が考えるべき
嶋田:確かに少し風邪ひいて咳が止まらないだけでも眠れなくなったりしますね。
鈴木:ADL低下に直結します。
また肺癌や結核など、見逃してはいけない咳もあります。
結核は決してまだ稀でなく、早期に診断しなければ感染が拡大してしまいます。

高齢者の咳では誤嚥の問題がいま、大きなウエイトを占めています。
誤嚥をどのように予防するか、誤嚥性肺炎にどのように対応するのかといったことは、
国民全体で考えるべきことではないでしょうか。

嶋田:貴院には嚥下障害のある高齢患者さんも入院されていらっしゃいますか。
鈴木:そうですね。
当院の4つの病棟のうち地域包括ケア病棟では、
誤嚥性肺炎の急性期で他院に緊急入院した患者さんを早目に引き受け、嚥下評価や嚥下リハビリを行い、
食べられる方はしっかり食べられるようにし、
食べられない方は今後どのような人生を過ごすかを一緒に考えるというスタンスで診療しています。
在宅復帰が困難な方の場合、
ご家族とともに少しでも良い時間を当院で過ごしていたいただくことも当院の役目の一つです。

後編に続く
Photo by Santos Izaguirre Jose Carlos




